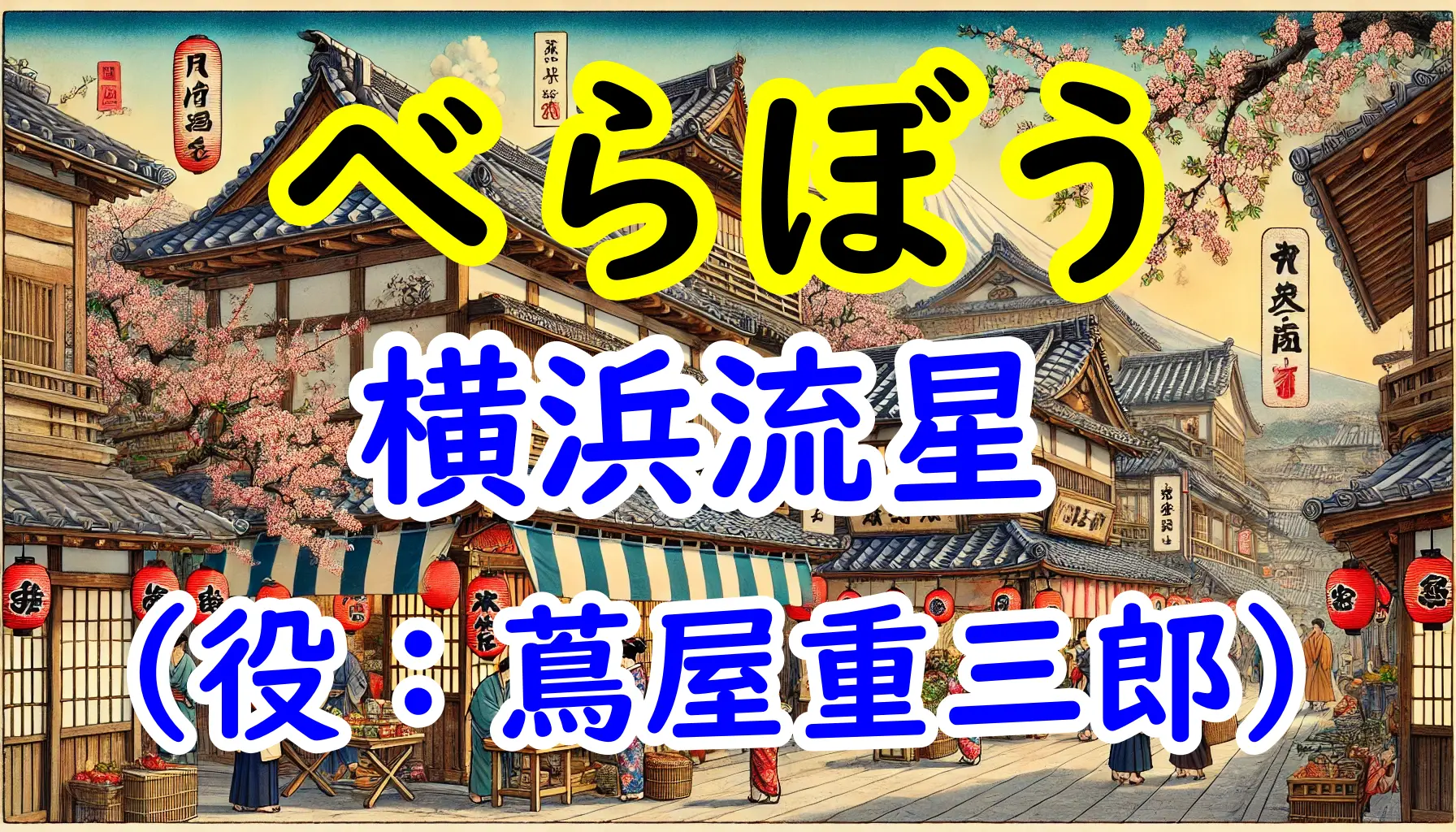横浜流星(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」で演じる「蔦屋重三郎」を紹介します。
大河ドラマでは珍しい江戸時代中期の時代背景です。この時代の大河ドラマは1995年の西田敏行が主役を演じた「吉宗」以来です。
また主人公は「蔦屋重三郎」という大河で取り上げないと一般人としては聞くことがなかった人物です。
しかしながら「蔦屋重三郎」は誰もが知っている「歌麿や写楽そして北斎」を世に出した出版・浮世絵ビジネスを手掛けたプロデューサーなのです。
それでは彼はいったいどんな生涯を送ったのでしょう。2025年大河ドラマを通して「蔦屋重三郎」の生涯を一緒に見守っていきましょう。
もしあなたが、「べらぼう」の蔦重を見逃してしまったなら…
アマゾンプライムビデオのサブスク「NHKオンデマンド」で再視聴して下さいね。
詳細はこちら。
⇒アマゾン(amazon)プライム会員は「大河ドラマ」を「NHKオンデマンド」で観る。
横浜流星(キャスト)が「べらぼう」で演じる「蔦屋重三郎」とは。
死没:寛政9年(1797年5月6日)(47歳没)
本名:喜多川 柯理(喜多川氏の養子)
蔦屋重三郎は寛延3年(1750年)江戸の吉原で生を受けます。本名は、丸山柯理(からまる)で父は尾張出身の丸山重助、母は江戸出身の広瀬津予です。
幼少期、「蔦屋」の屋号で商家を営んでいた喜多川氏の養子に入り、通称を重三郎と名乗ります。
寛政9年(1797年)までの47年の生涯です。
江戸幕府8代将軍徳川吉宗の時代に生を受け、9代将軍徳川家重、10代将軍徳川家治の時代から11代将軍徳川家斉の時代で没しています。
蔦重は江戸時代(安永・天明・寛政期)の出版界を代表するヒットメーカーでありカリスマ経営者でした。
小さな貸本屋から始まり、一代で江戸きっての有名版元(出版社発行人)に成り上がっていきます。10代将軍徳川家治の時代から描かれる「べらぼう」
蔦屋重三郎の生涯をアマゾン(amazon)プライムの「NHKオンデマンド」で一緒に観て下さいね。
アマゾン公式⇒アマゾンプライムビデオの「NHKオンデマンド」
蔦屋重三郎(蔦重)と花の井(改め瀬川)との関係は?
蔦屋重三郎(蔦重)と花の井は幼馴染、いわゆるソウルメイトなんです。二人は幼い時から吉原で過ごし、楽しい夢を語っていました。
ですが、第9話では、吉原からの足抜けを計画しますが、断念し瀬川は検校の嫁になりましたが、第14話で離婚し吉原に戻ってきます。
これで晴れて二人は夫婦になれると思いきやなぜか瀬川は吉原を後にします。第1話から登場していた花の井改め瀬川は第14話で退場しています。続きは下記の記事で…
「べらぼう」のあらすじ(ネタバレ)感想のまとめはこちら。
花の井改め瀬川を演じた「小芝風花」は第14話で寂しいですが退場します。
「べらぼう」で演じるキャストの一覧はこちら。
蔦屋重三郎(蔦重)の誕生。
蔦重は寛延3年(1750年)1月7日に江戸の遊廓・吉原で生まれました。7歳の時に両親が離婚し、吉原で引手茶屋「蔦屋」を経営する喜多川氏の養子になります。
引手茶屋とは、酒や食べ物を提供しつつ客の希望などを聞き、それに合わせた妓楼と遊女を手配してくれる「吉原の案内所」のような場所です。
現代のネット社会でいえば「マッチングアプリ」などの「場を提供する場所」ですね。
- 本名:丸山柯理(からまる)
- 父:丸山重助(尾張出身)
- 母:広瀬津予
蔦重の親戚縁者の多くは「廓者」として廓内で働いていました。
蔦屋重三郎が生まれ育った吉原とは。
物語は、明和9年(安永元年1772年)の「明和の大火」から始まります。
蔦屋重三郎(蔦重)が登場するこの場所は新吉原と呼んでいます。
というのも元々吉原は、日本橋葺屋町(ふきや)現在の東京都中央区日本橋人形町2丁目付近にありました。
しかし、明暦3年(1657年)の明暦の大火で全焼したのと、幕府公認の遊郭が江戸の中心にあるのはよろしくないとのことで移転してきたのです。
新吉原は明和5年(1768年)にも全焼しています。しかし、吉原の守護神、「九郎助稲荷(くろすけいなり)」だけが2度の大火でも焼けずに残りました。
現在は吉原神社(東京都台東区千束三丁目)に縁結び、所願成就、五穀豊穣の神様として祀られています。
「べらぼう」では綾瀬はるかさんが「九郎助稲荷(くろすけいなり)」として語りを務め、重三郎の活躍を見守っていきます。
新吉原の役割。
蔦屋重三郎は生まれも育ちも江戸の新吉原です。その新吉原はどんな役割を持っていたのでしょうか。
幕府公認の遊郭・吉原は、江戸の二大悪所といわれる一方、文化人が集うサロン的な役割を果たす場となっていました。
そのような特殊な環境で生まれ育った蔦重が自らの出目を最大限に活かし、江戸の出版界にのし上がっていくのです。
その幕府公認の遊郭・吉原とは…。
蔦屋重三郎の出版原点は貸本屋。
「べらぼう」は蔦重の青年期から描かれます。
22歳になった蔦重は、吉原大門前「五十間道」にあった義兄・蔦屋次郎兵衛が営む「引手茶屋」の軒先を借りて、貸本屋兼書店の「耕書堂」を開業しました。
「耕書堂」は「書物を耕す」という意味があります。耕書堂は純粋な書店というよりは、出版業者兼書店です。
出版界に刺激を与えて新機軸の書物を刊行したい、さらには出版界そのものを変えたいという、重三郎の熱き志が込められているのですね。
「べらぼう」では平賀源内先生が名付けの親ですね。
蔦屋重三郎成功の原点(吉原ガイドブックを企画)。
蔦重の成功は「吉原細見」という遊廓のガイドブックが原点であり出発点です。明治の本はこんな感じです。
明治の⇒吉原細見
「吉原細見」とは。
吉原細見とは、吉原内の略地図をはじめ、妓楼の場所や遊女の名前などが記載されていました。通常、春と秋の年2回発行されていました。
実用的なガイドブックとしてだけでなく、江戸みやげとしての需要もあり、隠れたベストセラーだったといいます。
「吉原細見」は鱗形屋が独占販売。
ただ、当時「吉原細見」は、江戸の大手版元である鱗形屋の孫兵衛が独占販売をしていました。
(孫兵衛を演じるのは片岡愛之助)
しかし遊女の出入りが激しいにもかかわらず、あまり改訂されずに情報が古いことも多く情報誌としての信用が落ちていました。
このままでは売り上げに響きます。そこで情報をアップデートするために「細見改め」に抜擢されたのが蔦重だったのです。
蔦屋重三郎は「吉原細見」企画編集の下請け。
「細見改め」とは今でいうリサーチャー兼編集者で、遊女の最新情報などを集めて新しい「吉原細見」を企画編集する仕事でした。
吉原で生まれ育ち、人脈がある蔦重にはぴったりの役割といえます。
蔦重は、鱗形屋の下請け(編集プロダクション)として、「吉原細見」の企画編集に携わるようになります。
蔦屋重三郎は遊女のカタログ「一目千本」を出版プロデュース。
安永3年(1774年)蔦重24歳の時に、絵師の北尾重政に委託し遊女を花に見立てた遊女評判記「一目千本」を出版しました。
蔦屋重三郎の「吉原細見(一目千本)」が大ヒット。
吉原細見のヒット要因その1。アップデート。
蔦重の「吉原細見」の大ヒットの要因の一つに「最新の情報にアップデート」をあげることができます。
それまでの「吉原細見」は、情報が古かったり間違っていたりすることが多く、信頼性に欠けていました。
そこで、蔦重は店を回って最新の情報に書き換えました。
店や遊女の格付けや詳細な料金などの情報も充実させたのです。吉原の事情通である蔦重にはうってつけでした。
吉原細見のヒット要因その2。ブランド力。
蔦重が細見改めとして最初に関わった「吉原細見」のタイトルは細見嗚呼御江戸。その序文を人形浄瑠璃の人気作家・福内鬼外に依頼しました。
福内鬼外と聞いてもピンとこない大河ファンも多いと思いますがコピーライターの「平賀源内」のペンネームです。
べらぼうでは、安田顕さんが演じますので期待大です。平賀源内は、エレキテルの発明や土用のウナギなどで有名なマルチクリエイターです。
平賀源内の序文は大きな話題を呼びました。
その後も、序文には朋誠堂喜三二や尾美としのり、跋文などを起用し、あとがきは、四方赤良、大田南畝、
祝言狂歌を朱楽菅江という有名作家を起用しました。
いわば、有名人やベストセラー作家の序文で箔をつけ、「吉原細見」のブランドを高めることに成功したのです。
吉原細見のヒット要因その3。ユーザーファースト。
蔦重が版元となって最初に刊行された細見『籬(まがき)の花』は、今までの鱗形屋版細見から見た目が大きく変わりました。
「横長」から「縦長」になり、大きさも約2倍に判型を変更しました。これは現在の単行本の判型四六判とほぼ同じになります。
通りを真ん中に配置し、その両側に店を書き込む等、遊廓の位置関係をよりわかりやすくしました。
判型とレイアウトの変更で、ページ数を減らしたことにより、大幅なコスト削減に成功します。その分、安価で販売することができました。
「薄い、安い、見やすい」とユーザーファーストとして喜ばれたのです。
横浜流星(キャスト)が「べらぼう」で演じる「蔦屋重三郎」の出版業界。
版元・地本問屋の仕事とは。
当時、江戸で生産し消費を前提とする地物(じもの)の本を「地本(じほん)」と呼ばれていました。
逆に上方から江戸に運ばれるのは「下り本」です。
地本を扱う地本問屋は、企画立案から制作費の出資、印刷工程の監督、販路の確保、自店での販売まで全工程に携わり、統括者としての役割を果たすのです。
物語に登場する、鱗形屋や鶴屋は「地本問屋」で日本橋に店を構えており、蔦重の吉原時代の耕書堂はその仲間には入れませんでした。
蔦重の耕書堂が日本橋に進出するのはもう少し先ですね。
蔦屋重三郎が発掘したクリエイターたち。
「べらぼう」で「蔦屋重三郎(蔦重)」が描かれることは、当時の多くのクリエイターの作品が紹介されると言うことです。
なぜなら蔦重は江戸時代中期に本が大衆化し出版業界が変革を遂げた時期に活躍した出版業者(プロデューサー)だからです。
喜多川歌麿や葛飾北斎をはじめ、東洲斎写楽を世に送り出し、その他にも数多くの浮世絵師や作家の才能をプロデュースしています。
蔦重の本名は「喜多川珂理」です。
「重三郎」は通称であり、その他に狂歌名を「蔦唐丸」で、屋号は「蔦屋」、または「耕書堂」と言います。
- 喜多川歌麿(染谷将太):無名だった絵師を江戸きっての人気絵師に。
- 東洲斎写楽:謎の天才絵師。
- 葛飾北斎:蔦重の死後に大ブレイクする。
- 曲亭馬琴:無名時代から活動をサポート。
- 十返舎一九:無名時代から活動をサポート。
蔦屋重三郎が発掘した、喜多川歌麿。
蔦重の強い支援の元で花開いたすぐれた才能の持ち主です。
蔦屋重三郎はプロモーター。
蔦重は時代の流れを読み取る嗅覚に優れていました。数々の流行作家とタッグを組み、話題作を続々と世に出しました。
それでいて、いわゆるクリエイターであったわけではなく、経営者としても堅実な一面を持っていました。
現代でいうとベストセラーを連発する編集者兼出版社社長といったところでしょうか。
蔦屋重三郎の生涯一覧。
- 誕生:1750年(寛延3年)、吉原遊郭の勤め人「丸山重助」の子として吉原で生まれます。しかし幼くして両親と生き別れ、引手茶屋・喜多川氏の養子になりました。
- 書店開業:1773年(安永2年)23歳:吉原大門前に書店「耕書堂」を開きます。(貸本が主業務)。吉原の案内本である「吉原細見」の小売りを始めます。
- 出版物発行:1774年(安永3年)24歳:最初の出版物となる遊女評判記「一目千本」を刊行。
- 事業拡大:1780年(安永9年)30歳:本格的に出版業を開始。
- 日本橋に店を構える:1783年(天明3年)33歳:日本橋の通油町に店を構え、黄表紙をはじめ、洒落本や狂歌本、絵本、錦絵などを出版し、次々とヒット作を生み出す。
- 表紙が摘発:1791年(寛政3年):41歳:老中「松平定信の「寛政の改革」が始まり、山東京伝の洒落本や黄表紙が摘発されます。
- 弾圧:1791年(寛政3年):41歳:蔦屋重三郎は過料、山東京伝は手鎖50日という処罰を受けます。
- 東洲斎写楽の役者絵を出版:1794年(寛政6年):44歳:弾圧のなか、に東洲斎写楽の役者絵を出版。
- 死亡:1797年(寛政9年)、脚気により、47歳という若さで亡くなりました。番頭の勇助が「蔦屋重三郎」を襲名し、以降4代まで続きます。
蔦屋重三郎のビジネスモデルは令和の時代でも…。
令和の社会でも存在する「本屋や出版、版元」。
出版業界で働く方々やコンテンツを扱うエンターテイメントで生きる業界の方々はとても参考になる題材です。
貸本屋からビジネスを大きくしてきた蔦重は「プロモーター」の顔としてもその存在は偉大です。経営手腕を知りたい方には必見の大河ドラマです。
令和の時代はネット社会でAIが予測不能な勢いで進化しています。デジタルコンテンツもAIが主流となるでしょう。
ただ、歌麿や写楽などのクリエイターたちのアナログ技術の原点を知ることもとても有意義だと思います。
横浜流星(キャスト)が演じる「べらぼう」「蔦屋重三郎」の収益。
蔦屋重三郎の「吉原細見」以外の出版物。
蔦重は「吉原細見」以外に吉原からのオーダーでの贈答本やイベントのガイドブックも作りました。
制作費は発注元が出してくれるのでリスクはなく、定期的に発行されるので確実に利益があがりました。
他にも寺子屋の教科書なども手がけました。(現在の教科書出版社)薄利ながら長期にわたって同じものを刷れば一定の売り上げと利益が見込める商品です。
蔦屋重三郎の「吉原細見」収益は広告収入も。
このように、かゆいところに手が届く蔦重版の「吉原細見」は大ヒットしました。
春秋と2度の改訂版が出て、そのたびに一定の売り上げが見込めます。また吉原の各店からの広告収入もあります。
「吉原細見」の出版物で、蔦重は安定した収入を得ることができました。現在でも大手出版社はストックしているコンテンツが沢山あります。
重版になれば社も作家も潤います。
蔦重は耕書堂という小さな貸本屋から始め、その後のアイデアと実行力で安定した経営基盤を築き上げていくのです。
34歳の時、日本橋通油町(現在の中央区日本橋大伝馬町)に進出します。本店を構えます。
「黄表紙」「酒落本」「狂歌絵本」「錦絵」などのヒット作を次々とプロデュースして、時代の寵児となりブランドを確立しました。
当時の日本橋界隈。
江戸の商業・文化の中枢である日本橋界隈は、出版業においても、歴代の書物問屋や地本問屋が軒(のき)を連ねてきた一等地でした。
そこへの進出は、蔦重が名実ともに一流の版元として認められたことを示しています。
蔦重と狂歌。
天明期の蔦重の仕事して重要なのが、当時江戸で爆発的な流行を見せた「狂歌」に関する出版でした。
狂歌とは、和歌のパロディーのことで、伝統的な「五七五七七」の形式を用いつつ、世俗的な洒落や皮肉を歌に盛り込んで詠(えい)じる遊びです。
狂歌は原則、記録をとらずにその場で詠み捨てられていたものです。
横浜流星(キャスト)が演じる「べらぼう」「蔦屋重三郎」の試練。
蔦屋重三郎と寛政の改革。
天明7年(1787年)から寛政5年(1793年)にかけて行われた幕政改革は「寛政の改革」と呼ばれ、前年(天明6年)に失脚した田沼意次に代わった老中松平定信が中心となって断行されました。
「寛政の改革」が始まると、風紀取り締まりが厳しくなり、順風満帆だった蔦重の出版業も陰りが見え始めます。
蔦重の出版を支えていた武士作家たちが狂歌や戯作界から次々と去っていったのです。
蔦屋重三郎から去っていく武士作家。(太田南畝=なんぽ)
太田南畝(なんぽ)はわずか一年間の滞在で長崎弁を使いこなし、万人の笑みを誘う長崎情緒を歌い上げた江戸の狂歌師で別名は「蜀山人」
意次の腹心の土山宗次郎と懇意にしていたとのことが自らに不利に働くと懸念して活動を自粛しました。
第20話「寝惚けて候」で出会います。
⇒【太田南畝との出会い】大河ドラマ「べらぼう」のあらすじ(ネタバレ)と感想。第20話「寝惚けて候」
蔦屋重三郎から去っていく武士作家。朋誠堂喜三二と恋川春町。
黄表紙作家の朋誠堂 喜三二(ほうせいどう きさんじ)と恋川春町は、手がけた作品が政治を風刺する内容だったとして、両者とも断筆に追い込められました。
朋誠堂 喜三二の本名は平沢常富で、出羽国久保田藩(現在の秋田県)の定府藩士で江戸留守居役でした。
恋川春町の本名は倉橋 格。戯作者であり浮世絵師でもあります。「金々先生栄花夢」で黄表紙といわれるジャンルを開拓し、黄表紙の祖と評されました。
蔦屋重三郎と山東京伝の処罰。
狂歌・戯作出版の大きな柱を失った蔦重が頼ったのは若手の人気作家であった山東京伝でした。
黄表紙、洒落本、浮世絵など多彩な才能をみせていた京伝は早くから版元たちの注目の的でした。
しかし、「寛政の改革」の出版統制令は風刺取締を強く打ち出しています。時事的な内容禁止、好色本の絶版、華美で高価な出版物などはその対象です。
やがて山東京伝(さんとうきょうでん)の酒落本が摘発され、手鎖50日、版元の蔦重にも財産の半分を没収という厳罰が下されました。
横浜流星(キャスト)が演じる「べらぼう」「蔦屋重三郎」の復活。
蔦重の経営の危機を救ったのは歌麿でした。その作品は「婦人相学十躰」シリーズ。
歌麿の「婦人相学十躰」
「寛政の改革」後は喜多川歌麿の大首絵(おおくびえ)の美人画や無名の新人絵師東洲斎写楽の役者絵をプロデュースして復活します。
「婦人相学十躰」シリーズは、歌麿が美人画専門の絵師として本格的な活動を始めた頃の作品で、特徴は、モデルを半身像で促える大首絵形式を導入している点にあります。
婦人相学十躰の利点。
利点は二つあります。
1,顔を拡大して描くことになるため。目や眉、口元といった人物の表情を決めるパーツに繊細な変化がつけられ、モデルに生気と現実感を与えられる点です。
2,制作コストの削減です。一時代前の天明期は名所を背景に等身の高い女性を全身像かつ群像で描くことが主流でした。
しかし、背景や人物を多く描く分、堀摺の手間がかかります。歌麿はモデルを一人に絞り、背景を省くことで極力このコストを抑えることができました。
またそれが却ってモデルのしぐさ、着衣、髪型に観賞者の目を向けさせ、そこに含ませたニュアンスから人物の内面を読み取らせる趣向に成功しています。
統制令を回避。
歌麿の「婦人相学十躰」の連作は、華美で高価な出版物を禁止する統制令を回避した上に、新たな女性像を打ち出した画期的な美人画です。
「大首絵形式」は先行して役者絵に用いられていたが、それを美人画に取り入れる発想は、歌麿単独によるものではなく、蔦重のプロデュースによるもとと考えられています。
「べらぼう」ではどのように描くかワクワクしますね。
写楽がデビュー。
豪華な黒雲母摺(くろもらずり)による役者大首絵で、「東洲斎写楽」が蔦屋からデビューしました。
写楽の例もそうですが、蔦重は逆境をものともせず、冷静に時流を読み、かつ人をあっと言わせるものを常に創造してきました。
その挑戦は亡くなるまで続きます。
だからこそ、蔦重が手掛けた作品には普遍的な美しさ、面白さが見いだされていると思います。
写楽をもっと詳しく知りたい方は、「写楽 Sharaku (DVD)」をご覧下さい。
蔦屋と現代の「TUTAYA」の関係は。
まず、蔦屋(つたや)と聞くとCD&DVDのレンタル会社「TUTAYA」と関係があるのかと思う大河ファンも多いと思います。
結論は血縁関係はありません。詳しくはこちらで紹介しています。
まとめ。
1月から4月までは前編で第16話(4月20日放送)まで放送されました。物語は1週休んで17話(放送は5月4日)からは後編(第2章)に入ります。
まとめとして各話の視聴ポイントを並べました。
第1話:「ありがた山の寒がらす」
主人公・蔦屋重三郎(蔦重)が火災の中で人々を救助。田沼意次との出会い。
第2話:「吉原細見『嗚呼御江戸』」
吉原復興のため、蔦重が新しい『吉原細見』の制作を計画。平賀源内に「序文」を依頼し、吉原の魅力を再発信。
第3話:「千客万来『一目千本』」
蔦重が新しい入銀本『一目千本』の制作に挑戦。親子の葛藤や江戸の人間模様が描かれる。
第4話:「『雛形若菜』の甘い罠」
田安家存続を巡る賢丸の葛藤が描かれる。蔦重が錦絵『雛形若菜初模様』の制作に挑戦。
第5話:「蔦に唐丸因果の蔓」
蔦重が「改」の仕事に悩み、決断を下す。唐丸との別れや平賀源内の新たな商売が描かれる。
第6話:「鱗剥がれた『節用集』」
鱗形屋の窮地を救うため、蔦重が新しい青本作りに挑戦。幕府内での田沼意次と将軍・老中たちとの対立。
第7話:「好機到来『籬の花』」
蔦重が『吉原細見』を巡る出版競争に挑む。地本問屋の実力者・鶴屋喜右衛門との駆け引きが展開。
第8話:「逆襲の金々先生」
鳥山検校が登場。
第9話:「玉菊燈籠恋の地獄」
蔦重が商売と恋に悩む姿が描かれる。新之助とうつせみの逃亡計画とその結末が展開。
第10話:「青楼美人の見る夢は」
蔦重と瀬川が共に描いた夢を語り、青桜美人とは5代目瀬川のこと。その瀬川が鳥山検校へ嫁ぐ。
第11話:「富本、仁義の馬面」
富本節の太夫・富本午之助が登場。蔦重が午之助の誤解を解き、吉原の祭りに招くまでの奮闘が描かれる。
第12話:「俄なる『明月余情』」
吉原の夏祭りを巡る対立と、蔦重が祭りの盛り上げに奔走する姿が描かれる。平沢常富の助言や、若木屋と大文字屋の競争が展開。
第13話:「お江戸揺るがす座頭金」
江戸市中に座頭金(高利貸し)の悪行が描かれ、鳥山検校宅に奉行が…
第14話:「蔦重瀬川夫婦道中」
鳥山検校がお縄になり、瀬川は解放され、吉原に戻り蔦重と対面。二人は夫婦になるのか?
第15話:「死を呼ぶ手袋」
15話では田沼意次と敵対していた石坂浩二が演じる「松平武元」の最期が描かれます。物語では何者かが暗殺するのです。
第16話:「さらば源内、見立は蓬莱」
前編最後は蔦重にいろいろ影響を与えた平賀源内の最期が描かれました。16話は見ごたえがありました。
ここまで前編で17話から後編に入ります。
第17話:「乱れ咲き往来の桜」
蔦重が吉原に開店した「耕書堂」が時の大ムーブを呼び込むのです。
大河ドラマ俱楽部の管理人です。
NHK大河ドラマをこよなく愛し毎週楽しみに視聴しています。
ただ視聴するだけでなく「あらすじと感想」を紹介しています。
でもリアルタイムで見ることができない時は見逃し配信で見たり
時々は歴代の大河も視聴しています。
また、管理人の大好きな大河ドラマ出演者の他のドラマや映画を
まとめていますので見逃し配信と一緒に楽しんで下さい。
※大河ドラマ倶楽部は、Amazonの商品を紹介することで紹介料
を頂くAmazonアソシエイト・プログラムの参加者です。