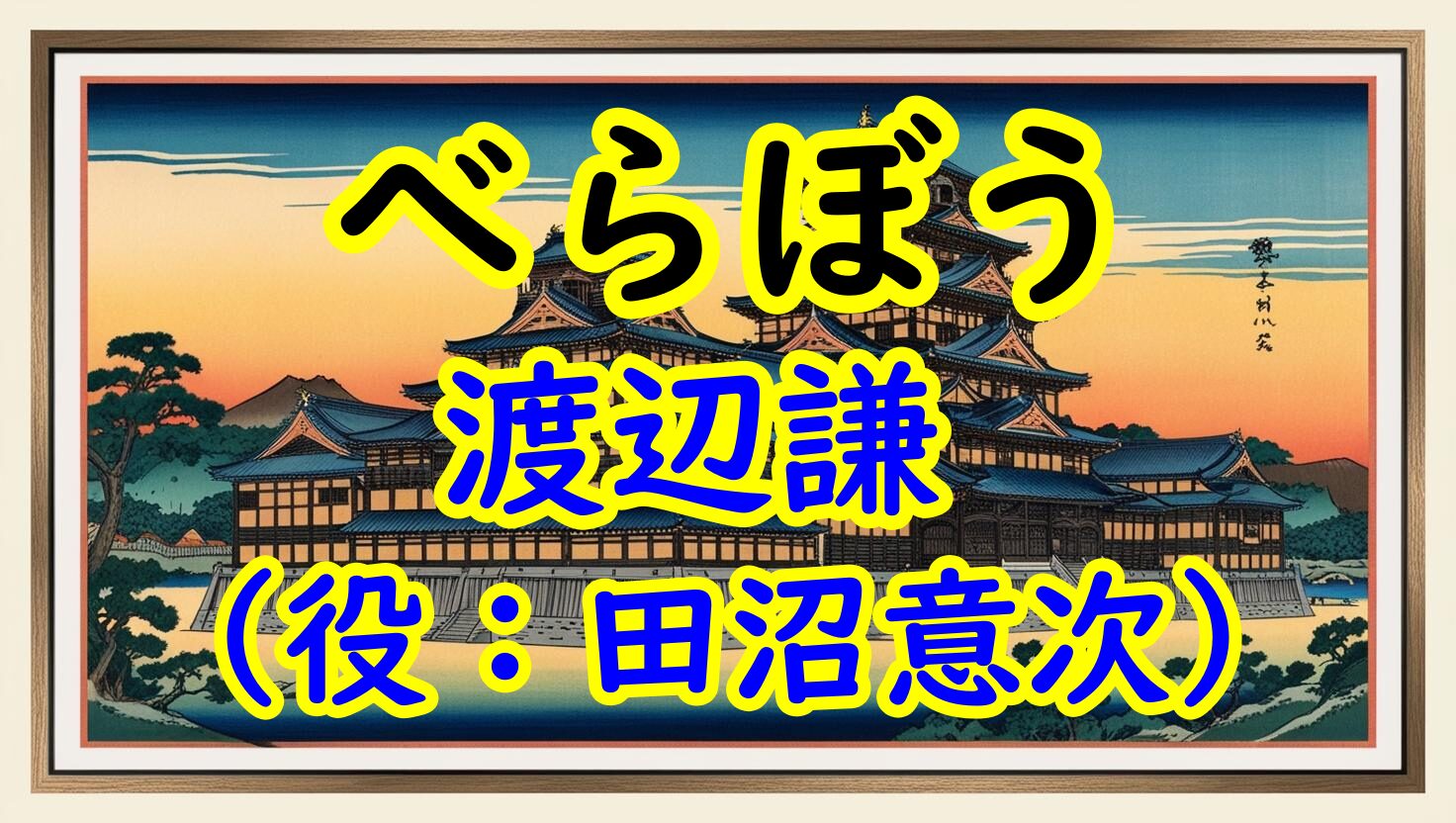渡辺謙(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」で演じる「田沼意次」を紹介します。
「べらぼう」は大河ドラマでは珍しい江戸時代中期の物語です。この時代は、「田沼意次」政権期で天明文化と呼ばれる町人文化の隆盛期でした。
ただ、田沼意次の評判は「金権腐敗の賄賂政治家」と斬新な経済政策を打ち出す「革新政治家」と言う、極端な二面性をもっていました。
はたして、「べらぼう」ではどちらの「田沼意次」を描くのか、とても興味深く楽しみにしています。
渡辺謙は1987年放送の大河ドラマ「独眼竜政宗」で主役の伊達政宗を演じ、驚異的な視聴率39.7%という大河ドラマ史上最高の平均視聴率を獲得しましたね。
大河ドラマ出演は「べらぼう」で6作目です。
さて、“べらぼう”であなたの推しキャストは誰ですか?べらぼうは個性派キャストが勢ぞろいしています。
もちろん主人公の横浜流星が演じる「蔦屋重三郎」の生き方に共感する大河ファンは多いと思います。
そこで、「“あの一言”で心掴まれた! 印象に残るセリフをもう一度観たい!聞きたい」と思ったあなた!
アマゾンプライムビデオのサブスク「NHKオンデマンド」をお勧めします。
\NHKオンデマンドは月々990円/詳しくはこちらから。
渡辺謙(キャスト)が大河ドラマ「べらぼう 」で演じる田沼意次とは。
死去: 天明8年(1788年7月27日)70歳。
田沼意次が歴史に登場するのは、江戸時代中期に側用人・老中として幕政の実権を握っていた明和4年(1767年)から天明6年(1786年)です。
印旛沼の開拓、 蝦夷地の開発、商業資本の利用など積極的な政策をとりますが、一方では賄賂政治の評判も浮かびあがります。
田沼時代は天災が多発しますが、「べらぼう」でも描かれる「明和の大火」では死者は1万4700人、行方不明者は4000人を超えたと言われています。
その後も天災地変は続きました。ガイドブックはNHK出版から発行しています。大河ファンとしては保存しておきたいムックですね。
【楽天のガイドブック】
楽天⇒大河ドラマ「べらぼう」前編のガイドブックはこちら⇒2025年「べらぼう」前編(第1話~第16話)
⇒大河ドラマ「べらぼう」後編のガイドブックはこちら⇒2025年「べらぼう」後編(第17話~第32話)
【アマゾンのガイドブック】
アマゾン⇒大河ドラマ「べらぼう」前編のガイドブックはこちら⇒2025年「べらぼう」前編(第1話~第16話)
アマゾン⇒大河ドラマ「べらぼう」後編のガイドブックはこちら⇒2025年「べらぼう」後編(第17話~第32話)
田沼意次が活躍する「べらぼう」のあらすじ(ネタバレ)と感想の一覧はこちら。
田沼意次は足軽の子から老中へ。
元は足軽だった家の出身ながら、優れた政治能力により幕政の中心に上り詰めます。
10代将軍徳川家治からも重用され、明和4年(1767年)には、吉宗によっていったん廃止されていた側用人に任じられます。
5年後には側用人の職務を続けたまま老中に昇格しました。「足軽の子」が幕閣の最高位まで上り詰めたのです。
これだけの劇的な出世は極めて異例なことでした。しかも意次の立場は、老中兼側用人という前例なきものでした。
政治の全権を握った意次は、改革に着手するのです。
田沼意次の政治改革。
殖産興業を重視した政治を行います。
新貨幣の鋳造、鉱山開発、蝦夷地開発など先進的な経済政策に取り組み、米中心の経済から貨幣経済へと移行しようとした政治家です。
また、疲弊した幕府の財政を削ってまで「御三卿」を存続させる必要はないとの考えも持っていました。
将軍家の血筋は「御三家」がありますからね。非常にリアリストな政治家だったのではと思います。
渡辺謙が大河ドラマ「べらぼう 」で演じる田沼意次と平賀源内の関係。
田沼意次は、第9代将軍徳川家重と第10代家治の治世下で側用人と老中を兼任して幕政を主導していました。
この期間を「田沼時代」と呼びます。田沼意次は平賀源内にほれ込み、特命を託すほど目にかけ町人文化の発展にも積極的でした。
「べらぼう」では田沼意次がどの時代から描かれるのか?放送前は分かりませんでしたが、第1話から登場しましたので、前編の主要人物として描かれることでしょう。
⇒大河ドラマ2025年「べらぼう」第1話「ありがた山の寒がらす」のあらすじ(ネタバレ)と感想。
田沼意次と平賀源内。
田沼意次は平賀源内のパトロンとしても有名ですので、源内に求めていたのが何かが分かると田沼政治が理解できますね。
源内はエレキテルの作成で良く知られていますが、その見物には意次の側室や息子の意知・意正が源内宅を訪れていました。
他にも源内はさまざまな分野に通じていました。
鉱山開発の技術者であり、秩父の中津川金山の採掘や秋田の院内銀山・阿仁銅山での指導を行っていました。
第5話では源内が秩父の鉱山開発に失敗し、意次が源内に出資するシーンが描かれましたが、二人の関係は江戸中期政治の骨太施策なのですね。
⇒大河ドラマ2025年「べらぼう」第5話「蔦に唐丸因果の蔓(つる)」のあらすじ(ネタバレ)と感想。
田沼意次が平賀源内に求めていたのは。
意次が源内に求めていたのは、鉱山技術者としての能力でした。
貨幣用の銀・鉄や輸出用の銅の増産が政策的に求められており、そのために意次は源内を支援したのです。
源内は田沼期特有の社会・政治的な要求の下で活躍した文化人でした。
⇒安田顕(キャスト)が大河ドラマ「べらぼう 」で演じる平賀源内とは。
渡辺謙が大河ドラマ「べらぼう 」で演じる田沼意次と蔦屋重三郎の関係。
田沼意次と蔦屋重三郎の接点は。
田沼意次と蔦屋重三郎の接点は「べらぼう」ではどのように描かれるでしょうか?
第1話「ありがた山の寒がらす」では、エンディングで蔦重が意次の屋敷に訪れて吉原の現状を話すシーンが最初の接点です。
蔦重は意次からの言葉で目が覚める思いをするのです。それは、蔦重が今後携わる「吉原細見」のヒントになったと思われます。
「吉原細見」の詳細は「蔦屋重三郎」の紹介記事に掲載しています。
⇒横浜流星(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう」で演じる蔦屋重三郎とは。
「べらぼう」で演じるキャストの一覧はこちら。
渡辺謙が演じる田沼意次「田沼時代」の政策。
停滞した社会構造の中で先進的な主張が通らない状況は現代社会(令和)に通じていると思います。
江戸時代中期でも、老中首座の松平武元に嫌味を言われることもしばしばでした。田沼意次の政策は、商業や産業を活用した経済成長を目指す挑戦的なものでした。
田沼意次の政策は「重商主義政策」
意次が取り組んだ政治改革の大きな特色は、重商主義政策でした。商人層力を活用し、間口の収入を増やすことを重視しました。
特定の商人に独占的な特権を与え、人々からの意見の献金(営業税)を受け取りました。 米の生産に依存した封建経済から、貨幣経済を活用した新しい収益構造を目指したのです。
年貢米に依存する幕府の財政構造の限界を知った意次は、商業の活性化によって幕府の財政再建を図ります。
年貢の増収よりも商品生産や流通によって財源を確保することが基本の考え方でした。
田沼意次の政策「株仲間の奨励」
商業団体である株仲間(現在の商工会のような組織)を奨励し、流通の効率化を図りました。これは吉宗が勧めた「享保の改革」の延長線上にあります。
株仲間に販売や仕入れの独占権を認める代わりに、運上・冥加金と呼ばれる税金を納めさせました。
意次は株仲間の公認をさらに拡大して税収入の増加を図るとともに、物資の流通をコントロールして供給の安定を図りました。
田沼意次の政策「鉱山開発と産業振興」
金山や銀山の開発を積極的に進めました。幕府直轄の鉱山で産出量が減少する中、平賀源内を登用して新しい鉱山開発に力を入れます。
第5話では源内が秩父の地本住民を説得して鉱山開発に取り組むシーンが描かれました。
田沼意次の政策「長崎貿易の活性化」
中国やオランダとの貿易による金・銀の海外流出を防ぐため、吉宗の方針を継承し、それまで輸入品に頼っていたサトウキビや朝鮮人参などの国産化を進めます。
本部の管理下で行われていた長崎貿易を活性化させ、
金・銀に代わる輸出品として俵物(干しアワビ、いりこ、ふかひれなどの海産物)の集荷に力を入れ、中国やオランダとの取引易さを拡大しました。
田沼意次の政策「新田開発」
農業生産を増やすための新田開発を推進しました。製塩業や漁業などの産業も奨励し、地方経済の活性化を図りました。
蝦夷地開発。
意次の視線は海外にも向けられました。ロシアの南下を警告し、仙台藩医・工藤平助が書いた「赤蝦夷風説考」が献上されると、調査隊を派遣して蝦夷地を調査させます。
さらに、ロシアと正式な貿易関係を結んで国益を増進させようと企てます。こうした先進的な発想は、当時の幕閣にはないものでした。
渡辺謙が演じる田沼意次「田沼時代」の政治。
田沼意次は大変な野心家でした。吉宗と共に江戸入りした旧紀州藩士の子である意次は幕府においては新参者でこれといった人脈はありません。
田沼意次の政治戦略。
意次は安永元年(1772年)老中に昇格した後も、松平武元(ドラマでは石坂浩二)を筆頭に先輩老中がいて意次がすぐに幕府を仕切ることはできませんでした。
しかし、意次は、息子や娘たちの結婚を通して幕府の有力者や大名たちと次々に縁戚関係を築き、人脈を広げていきます。
さらにその人脈を利用して大奥の女性たちにも贈り物を届け、味方を増やしていきました。
新しい政治戦略を持っている意次ですが人脈作りは古臭くとも有意義であると考えていたのでしょう。
結果として、老中のほとんどは意次の親戚になり、武元ら先輩老中がいなくなると、意次に逆らえる者はいなくなりました。
さらなる人脈作り。
意次は、徳川将軍家の親戚である「一橋家」とも関係を築いていきます。一橋家は吉宗・家重の時代に創設された「御三卿」の一つです。
将軍家に男子がいない場合には後継者を出す役割を持っていました。
- 意次の妻が一橋家の家老の娘。
- 弟の田沼意誠が一橋家の家老。
安永8年に家治の子・徳川家基が亡くなると、一橋当主だった徳川治済の長男豊千代(後の11代将軍・家斉)が家治の後継者と決まりました。
ただ、意次と「御三卿」の一つである「田安家」との関係は良好ではありません。
田沼意知が若年寄に。
天明3年(1783年)には、意次の長男・意知が老中に次ぐ地位である若年寄に出世しました。意次の政治基盤はますます盤石になりました。
しかし、意知が江戸城中で殺害される事件が起き、これが意次失脚の前触れとなりました。
渡辺謙が演じる田沼意次「田沼時代」の終焉。
田沼意次の政策「批判」
田沼意次の政策は一部では成功を覚悟しましたが、問題も多く残りました。その典型的なのが政治腐敗でしょう。
商人の癒着やカバー賂の横行が問題視され、「田沼時代は金の時代」と批判されました。
また、田沼の時代には浅間山の噴火( 1783年)や天明の大飢餓(1782年~1787年)が発生し、多くの庶民が苦しい生活を余儀なくされたのです。
田沼意次の政策「改革の限界」
武士社会が基本的に農業中心の封建制度を基盤としていたため、商業重視の田沼の政策は旧体制の支持者は田沼政策には不支持でした。
田沼意次の政策「失脚」34話。
天明6年(1786年)、大飢饉が続くなか、異常乾燥と洪水が重なって再び大凶作となり、食糧不足が長引いていた年に田沼意次は失脚しました。
松平定信が老中首座に、34話。
松平定信が老中として登場します(32話)。定信の政策は「寛政の改革」として田沼政治とは対照的なものでした。
近代的な経済観を持った田沼意次。しかし、当時の社会構造と不一致したのが要因なのかは定かではありませんが、挫折しました。
「べらぼう」ではどのような描き方をするのか、34話で定信は老中首座に、そして意次は失脚します。
⇒【質素倹約に抗う蔦重】大河ドラマ2025年「べらぼう」第34話「ありがた山とかたじけ茄子」のあらすじ(ネタバレ)と感想。
まとめ。
意次の政治は、社会に自由な気風をもたらしました。その風を受けて様々な芸術や娯楽が発展し、蔦屋重三郎という希代なプロデューサーが生まれたのです。
「べらぼう」では、商業政策を実行する前の段階ですが、源内との会話で垣間見ることができます。
その頂点は何話で紹介されるのでしょうか。ぜひアマゾンプライムの「NHKオンデマンド」で視聴して下さい。
大河ドラマ俱楽部の管理人です。
NHK大河ドラマをこよなく愛し毎週楽しみに視聴しています。
ただ視聴するだけでなく「あらすじと感想」を紹介しています。
でもリアルタイムで見ることができない時は見逃し配信で見たり
時々は歴代の大河も視聴しています。
また、管理人の大好きな大河ドラマ出演者の他のドラマや映画を
まとめていますので見逃し配信と一緒に楽しんで下さい。
※大河ドラマ倶楽部は、Amazonの商品を紹介することで紹介料
を頂くAmazonアソシエイト・プログラムの参加者です。