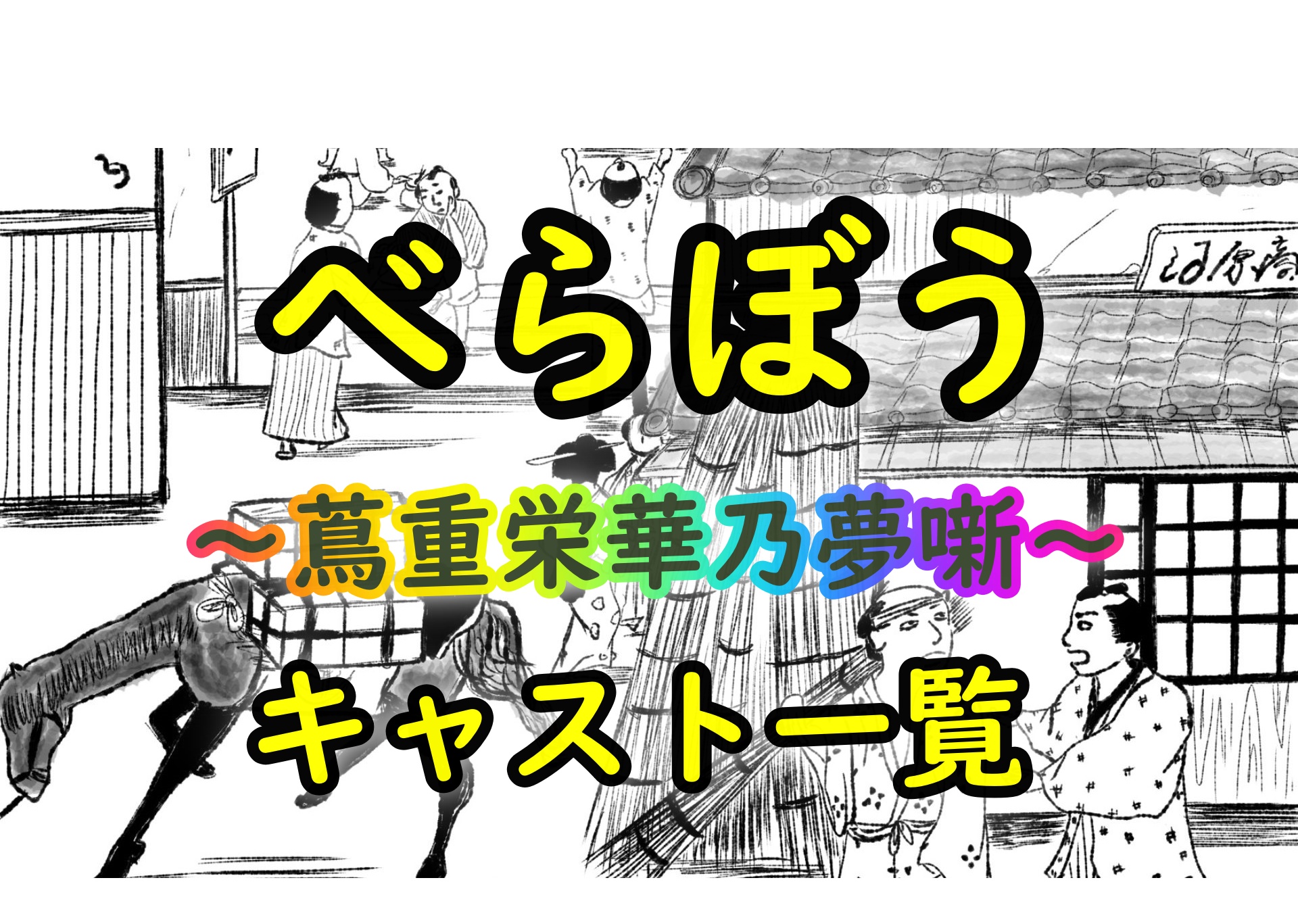豪華キャストが出演する大河ドラマ2025年「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~(つたじゅうえいがのゆめばなし)の配役を一覧で紹介します。
主人公は大河ドラマ初出演で初主演の横浜龍星さんで、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・蔦屋重三郎(蔦重)です。
現代で言えば芸能メディア界の辣腕プロデューサーですね。
前編の第1話から第16話までは蔦屋重三郎こと蔦重が吉原での生きざま(色恋)から「耕書堂」を開くまでが描かれます。
アマゾン⇒大河ドラマ「べらぼう」第壱集dvd
アマゾン⇒大河ドラマ「べらぼう」第壱集Blu-ray
楽天ブックス⇒大河ドラマ「べらぼう」第壱集dvd
楽天ブックス⇒大河ドラマ「べらぼう」第壱集Blu-ray
後編の第17話から第32話までは吉原の「耕書堂」が繁盛しポップカルチャーの礎を築き、その後、吉原の耕書堂は江戸の中心地日本橋に移ります。
完結編の第33話から第48話(最終話)までは蔦重の商才が発揮され日本橋耕書堂が発展します。しかしときに“お上”に目をつけられ苦難が、そして蔦重の最期が最終話で描かれます。
蔦重は、“面白さ”を追求し続けた人物で、喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝、滝沢馬琴を見出し、日本史史上最大の謎のひとつ“東洲斎写楽”を世に送り出します。
「謎の人物写楽」をどのような形で演出するか?キャスト登場はありうるのか?この脚本も注目ポイントです。
さて、喜多川歌麿は染谷将太(18話で登場)が、山東京伝は古川雄大(13話で登場)と豪華なキャストが演じます。
あなたがプライム会員でこの豪華な俳優(キャスト)が出演する「べらぼう」を見逃したなら、アマゾンプライムビデオの「NHKオンデマンド」でイッキ見して下さい。
まだプライム会員になっていない大河ファンはお買い物の配送料が無料になり数多くの映画とドラマが視聴できるので登録することをお勧めします。
- 大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧。吉原の蔦屋や日本橋耕書堂の人々。
- 大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧。吉原で忘八と呼ばれた女郎屋、引手茶屋。
- 大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧。吉原の女郎たち。
- 小芝風花(役:松葉屋の花魁、花の井=五代目瀬川)14話で退場。
- 前田花「子役:幼少時代の花の井(あざみ)」
- 小野花梨(役:松葉屋の座敷持ち、うつせみ)12話で退場しますが…。
- 久保田妙友(役:松葉屋の花魁、松の井)18話で退場。
- 珠城りょう(役:松葉屋の番頭新造、とよしま)
- 山下容莉技(役:まさ)
- 愛希れいか(役:元・松葉屋の花魁、朝顔)
- 中島璃菜(役:二文字屋の女郎、ちどり)大河初出演。
- 稲垣来泉(役:大文字屋の振袖新造。かをり)大河初出演。
- 福原遥(役:大文字屋の花魁。誰袖)17話で登場。
- 山村紅葉(役:志げ)
- 東野絢香(役:玉屋の座敷持ち、志津山)
- 大塚萌香(役:「桐菱屋」の女郎亀菊)
- 新井美羽(役:女郎屋・松葉屋に売られてきた武家の娘・さえ)
- 大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧。市井の人。
- 大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト。語りは綾瀬はるか。
- 大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧。蔦重と関係が深い人物。
- 大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧。クリエイターたち。
- 染谷将太(役:喜多川歌麿) 18話で登場。
- 尾美としのり(役:朋誠堂喜三二(ほうせいどうきさんじ) 本名は平沢常富。
- 古川雄大(役:山東京伝(さんとうきょうでん) 本名は岩瀬醒)
- 岡山天音(役:倉橋 格 /恋川春町)19話で本格登場し36話退場(切腹)。
- 桐谷健太(役:四方赤良(あから)本名は大田南畝)20話で登場。
- 片岡鶴太郎(役:鳥山石燕)18話で登場、35話で退場(死亡)
- ジェームス小野田(役:狂歌師・元木網=もとのもくあみ)大河ドラマ初出演
- 寛一郎(役:富本午之助=富本豊前太夫)
- 濱尾ノリタ(役:市川門之助)
- 山中 聡(役:杉田玄白)
- 山口森広(役:唐来三和)
- 浜中文一(役:朱楽菅江)
- 橋本淳(役:北尾重政、絵師)
- 前野朋哉(役:勝川春章、絵師)
- 鉄拳(役:礒田湖龍斎)
- 水樹奈々(役:狂名“智恵内子=ちえのないし)大河初出演。20話で登場。
- 加藤虎ノ介(役:北川豊章=絵師)18話で登場。
- 又吉直樹(役:宿屋飯盛)
- 井上芳雄(役:十返舎一九(じっぺんしゃいっく) 本名は重田貞一)
- くっきー!(役:勝川春郎後の葛飾北斎)
- 津田健次郎(役:滝沢瑣吉後の曲亭馬琴)大河初出演。
- 登場しません。(役:歌川広重)
- キャスト不在(役:幻の東洲斎写楽)
- 登場しません。(役:菱川師宣(ひしかわもろのぶ)
- 大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧。本屋たち。
- 大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧。徳川家。
- 大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧。幕臣と旗本。
- 大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧のまとめ。
大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧。吉原の蔦屋や日本橋耕書堂の人々。
大河ドラマ「べらぼう」の前編では、吉原の一角にひっそりと構える蔦重の貸本屋・蔦屋が登場します。
店を切り盛りするのは、まだ若く才気にあふれた蔦重と、彼を支える謎の少年・唐丸や奉公人の留四郎が貸本の管理を行い、吉原遊郭の客や芸者に貸本を届けていました。
やがて蔦重は日本橋へ進出し、本屋・耕書堂を開店。
ここでは商売の規模が一気に拡大し、版木師、彫り師、摺り師といった職人たちが加わり、出版の総合拠点へと進化します。
帳場を任される番頭、店を支える下女・丁稚も増え、吉原時代の小さな貸本屋が、文化の発信地へと変貌していく姿が描かれます。
横浜流星(主人公:蔦屋重三郎)
幼いころに両親と生き別れ、江戸郊外の吉原で引手茶屋を営む駿河屋市右衛門の養子になりました。
市右衛門の息子である次郎兵衛が営む茶屋の蔦屋を手伝うかたわら貸本屋を展開します。さらに、衰退著しい吉原の再興と女郎たちの生活向上を目指して出版業に乗り出します。
地本問屋の抵抗に遭うなどその道のりは大変険しい道のりでした。
しかし、幼馴染の売れっ子花魁の「花の井」を始め、女郎屋の主人たち、発明家の平賀源内、幕府の要人・田沼意次など時代の寵児たちを巻き込みながら…
やがて、持ち前の機転と発想力で画期的な出版物を世に送り出すのです。
⇒横浜流星が大河ドラマ2025年「べらぼう」で演じる蔦屋重三郎とは。
高木波瑠「子役:幼少時代の蔦重・柯理(からまる)」
吉原で生まれ、両親に捨てられ、引手茶屋の駿河屋に引き取られました。吉原の遊郭文化の中で育ちます。
松葉屋の禿(かむろ)あざみ(後の花の井)とともに、第1話「ありがた山の寒がらす」で「愛希れいか」が演じる女郎の「朝顔」から本の世界の面白さの教えを受けました。
演じるは高木波瑠。大河ドラマは3度目の出演です。前回は(青天を衝け、光る君へ)
中村蒼(役:蔦重の義兄・次郎兵衛)
駿河屋市右衛門の息子で、蔦重の義理の兄です。
吉原に向かう手前の五十間道で茶屋の経営を任されてはいるが、実際の切り盛りは蔦重が行っています。
蔦重は、その軒先を借り、貸本屋も営んでいます。
次郎兵衛は、はやりもの好きでおしゃれに敏感、自由気ままな性格で、いわゆる「放蕩息子」で趣味に力を注いでいます。
⇒中村蒼(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる次郎兵衛とは。
水沢林太郎(役:蔦屋の奉公人・留四郎)
駿河屋の主人市右衛門は身寄りのない男子を集め、店の若い衆として奉公させています。
蔦重もその一人ですが、留四郎もとあることがきっかけで、“蔦屋”で蔦重と共に働くことになります。
⇒水沢林太郎(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる留四郎とは。
渡邊斗翔(謎の少年・唐丸)
蔦屋で蔦重と共に働く謎の少年です。明和の大火の際に蔦重に拾われて、この時から記憶を失っています。
自分の名前も分からないので蔦重は自分の幼名だった「唐丸」と名付けます。蔦重の出版業を手伝う中で画才を発揮、絵師への憧れを抱きますが、思わぬ邪魔が入ります。
そして、蔦重の前から姿を消してしまいますが、その唐丸が成長し歌麿に生まれ変わるのです。
⇒渡邊斗翔(子役キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる唐丸とは。
橋本愛(役:日本橋の地本問屋・丸屋の女将。蔦重の女房)
日本橋の地本問屋丸屋の女将で前夫の吉原通いがもとで丸屋が潰れたため、吉原出身の蔦重に店を買われることに反発します。
しかし、蔦重の本作りの情熱に触れる中で徐々に変化が生じてきます。何話で蔦重の女房になるのでしょうか。
⇒橋本愛(キャスト)が大河ドラマ「べらぼう」で演じるメガネの「てい」とは。
高岡早紀(役:蔦重の母親・つよ)
つよは蔦重のもとに突然戻ってくる母親です。蔦重が7歳の時に離縁し蔦重を置いて去りました。
その後、米の不作で食いあぐね、蔦重の日本橋の店に転がり込みます。店の客に世辞交じりの髪結いをしながら蔦重の本を売り込みます。
対話力に長けた人たらし役ですね。高岡早紀は大河ドラマ3回目(元禄繚乱、軍師官兵衛)の出演です。(4月15日発表)
⇒高岡早紀(キャスト)が大河ドラマ「べらぼう」で演じる蔦重の実母「つよ」とは。
大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧。吉原で忘八と呼ばれた女郎屋、引手茶屋。
吉原で“忘八”と呼ばれたのは、遊郭の裏側を支え、ときに非情な判断を迫られる男と女です。
高橋克実演じる駿河屋市右衛門はその筆頭格で、金と欲が渦巻く吉原を熟知した商人で引手茶屋です。
蔦重の歩む道にも深く絡み、陰と情が交錯する存在です。
彼ら忘八は悪人ではなく、時代に翻弄されながらも生き抜いた“吉原のリアル”を体現する面々として描かれます。
高橋克実(役:駿河屋市右衛門)
吉原の引手茶屋“駿河屋”の主人です。引手茶屋とは、吉原に来た客に女郎を紹介する案内所です。
両親に捨てられた、幼い蔦重を養子にして育てあげます。
⇒高橋克実(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる駿河屋とは。
飯島直子(役:駿河屋の女将“ふじ”)
駿河屋の妻で、引手茶屋の女将。蔦屋重三郎(蔦重)の義理の母で、蔦重はじめ身寄りのない子どもたちを育て見守る慈愛の人です。
実の子である次郎兵衛を溺愛していています。
⇒飯島直子(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる駿河屋の女将“ふじ”とは。
正名僕蔵(役:松葉屋主人、松葉屋半左衛門)
代々“名妓(めいぎ)”としてその名を江戸中にとどろかす「瀬川」を輩出してきた老舗女郎屋“松葉屋”の主人です。
花の井ら数多くの女郎を抱え、花魁から禿まで、その数は50人以上とも、吉原の顔役で町の決めごとを取り仕切っています。
⇒正名僕蔵(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる松葉屋半左衛門とは。
水野美紀(役:松葉屋の女将“いね”)
代々、瀬川という伝説の女郎を輩出する老舗の松葉屋の女将です。いねもかつて花魁でしたが、主人に見初められ女将として見世の経営に携わります。
四代目・瀬川とは同年代であり、いつしか花の井に瀬川の名跡の“或るいわく”について語ります。
⇒水野美紀(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」で演じる「いね」とは。
長野里美(役:松葉屋の寮の管理人・はつ)
第14話で登場しました。
かたせ梨乃(役:二文字屋の女将“きく”)22話退場。
きくは、行き場のない女郎たちを抱える“河岸見世”「二文字屋」の女将です。きくもかつては吉原の女郎であり、年季があけて場末の女郎屋の経営を任されています。
かたせ梨乃が演じる「きく」は第22話「小生、酒上不埒にて(さけのうえふらちにて」で退場します。
⇒かたせ梨乃(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」で演じる二文字屋の女将「きく」とは。
伊藤淳史(役:大文字屋の主人、大文字屋市兵衛)19話退場(死亡)
新興勢力の女郎屋“大文字屋”の主人です。
愛称は“カボチャ” ドケチの“忘八” 。伊勢から江戸へ出て最底辺の河岸見世の女郎屋の経営から始め、中見世の女郎屋に店を拡大・成長させた経営手腕を持っています。
経費削減のため、女郎に安いカボチャばかり食べさせたことから“カボチャ”のあだ名を持ち、“ドケチ”として江戸中に知られ、子どもたちの口ずさむ歌にもなったといわれています。
⇒伊藤淳史(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる大文字屋市兵衛とは。
17話で心筋梗塞を発症に19話で遂に帰らぬ人となってしまいました。しかし第21話で二代目大文字屋として再登場します。
⇒【耕書堂繁盛の光と影】大河ドラマ「べらぼう」のあらすじ(ネタバレ)と感想。第17話「乱れ咲き往来の桜」
安達祐実(役:大黒屋の女将“りつ”)
吉原の女郎屋「大黒屋」の女将です。駿河屋、松葉屋、大文字屋、扇屋らと共に吉原を取りまとめ、蔦重の後見となります。
のちに女郎屋を廃業し、芸奴の見番となったあとは、蔦重が手がけた『富本本』や『浄瑠璃本』の出版に大きな影響を与えます。
⇒安達祐実(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう」で演じる「りつ」とは。
山路和弘(役:扇屋の主人、扇屋宇右衛門)
女郎屋“扇屋”の主人です。和歌、俳句、画に通じた教養人の松葉屋の主人と共に吉原を取りまとめています。
「墨河」という号を持ち、俳句、和歌、画などをたしなむ教養人で女郎たちにも和歌や書を習わせ、花扇、滝川といった名妓を育てました。
⇒山路和弘(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる扇屋宇右衛門とは。
本宮泰風(役:若木屋与八)
10話「青楼美人の見る夢は」で登場します。その後、忘八たち親父衆と対立します。
ただ第12話「俄(にわか)なる明月余情」ではエンディングで吉原の「俄祭り」が描かれ30日間踊り続けた若木屋の予八と大文字屋は仲直りします。
この「俄祭り」は現代にも通じる祭りですよね。ぜひ12話をご覧ください。
まだプライム会員になっていない大河ファンはお買い物の配送料が無料になり数多くの映画とドラマが視聴できるので登録することをお勧めします。
大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧。吉原の女郎たち。
小芝風花が演じる松葉屋の花魁・花の井は、吉原一とも噂される気品と才気を併せ持つ人気の花魁です。
美しさだけでなく、人情に厚く芯の強さを秘め、蔦重や吉原の人々にも影響を与える存在として描かれます。
彼女をはじめとした女郎たちは、過酷な環境の中でも誇りを失わず、自らの芸と心意気で客を魅了してきた“吉原の女たち”です。
華やかさの裏に、切なさと強さが息づく人間ドラマが光る存在となります。
小芝風花(役:松葉屋の花魁、花の井=五代目瀬川)14話で退場。
幼いころに親に売られ、蔦重こと蔦屋重三郎と兄弟のように育ってきた女性で、ひそかに蔦重に想いを寄せています。
吉原の老舗女郎屋・松葉屋を代表する“伝説”の花魁です。蔦重を助け、時に助けられながら、共に育った吉原の再興に尽力します。
やがて、とある理由から長らく途絶えていた伝説の花魁の名跡“瀬川”を継ぎ、その名を江戸市中にとどろかすこととなります。
五代目・瀬川は史実に残る“名妓”として知られ、1400両で落籍された出来事やその後の悲運な人生が戯作などで語り継がれることとなります。
ドラマでは第10話「青楼美人の見る夢は」で瀬川の最後の花魁道中が描かれました。白無垢姿の花魁道中です。
嫁ぎ先は「鳥山検校」で瀬川は吉原から離れ市井の女性(瀬似)となりました。その後、鳥山検校は高利貸しの件でお縄になります。
瀬川は離縁し吉原に戻り蔦重と幸せな時を過ごすのではと思いきや吉原から静かに去っていきました。
第14話「蔦重瀬川夫婦道中」で描かれます。この話で小芝風花が演じる瀬川は退場です。
⇒小芝風花(キャスト)が大河ドラマ「べらぼう 」で演じる花の井(五代目瀬川)とは。
前田花「子役:幼少時代の花の井(あざみ)」
花の井の幼少時は「あざみ」と呼ばれていました。両親に売られて、松葉屋に来ました。女郎見習いの禿(かむろ)として花魁の付き人を務め諸芸を学びます。
「柯理(からまる)=後の蔦重」からもらった赤本(幼児の絵本)「塩売文太物語」はあざみの宝物となります。
演じるは前田花。大河ドラマは初出演です。
小野花梨(役:松葉屋の座敷持ち、うつせみ)12話で退場しますが…。
女郎の格がトップではない「座敷持ち」です。幼いころから吉原で女郎として生きてきたうつせみの人生が大きく変わることになります。
「座敷持ち」は「呼出」の下のランクで、自分の客を接待するための座敷を持っている中堅の女郎です。
“花魁道中”は行わないが、禿や振袖新造がついて身の回りの世話をしてくれます。
うつせみは花魁の中でも非常に純粋な女性で、ある日客の新之助と恋に落ちます。もちろん色恋は吉原ではご法度です。
新之助との足抜けシーンが2度描かれます。足抜け後は浅間山で百姓をして生活するが、浅間山の噴火後江戸に戻ります。
江戸では蔦重の支援を受けながら子供も生まれ幸せな日々を過ごしていましたが、利根川の決壊後悲劇が襲います。
その結末は・・・
⇒小野花梨(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる「うつせみ」とは。
久保田妙友(役:松葉屋の花魁、松の井)18話で退場。
「呼出」は当時最高級の花魁であり、客からの指名を受けると禿や振袖新造を従えて引手茶屋まで客を迎えに行きます。
これを“花魁道中”と呼ぶます。松の井はトップの「呼出」であり、花の井の先を行く存在です。
⇒久保田紗友(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」で演じる「松の井」とは。
珠城りょう(役:松葉屋の番頭新造、とよしま)
とよしまは、松葉屋の「番頭新造」で、身請けされないまま年季を過ぎた松葉屋の元女郎です。
今は、松葉屋のもとで、禿や振袖新造の教育係である「番頭新造」を務める姉貴分で花ノ井について、身の回りの世話も務めています。
⇒珠城りょう(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう」で演じる「とよしま」とは。
山下容莉技(役:まさ)
松葉屋の遺り手です。
⇒山下容莉枝(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる“まさ”とは。
愛希れいか(役:元・松葉屋の花魁、朝顔)
蔦重と花の井を優しく見守り続けた朝顔。
最期は儚く散りましたが、撮影の合間にはたくさんの笑顔が✨
第1回見逃し配信中👇https://t.co/Q6zjapwsLz
朝顔 #愛希れいか
蔦屋重三郎 #横浜流星#大河べらぼう pic.twitter.com/nbB3wK2vZR— 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」1/5放送開始 (@berabou_nhk) January 8, 2025
幼少期の蔦重と花の井に赤本(子ども用の絵本)を読み聞かせ、蔦重が本の世界の楽しさ、面白さを知るきっかけとなった元・松葉屋の花魁です。
しかし今は体を壊し、きくのもとに身を寄せています。そんなある日、朝顔は帰らぬ人となってしまいます。
第1話「ありがた山の寒がらす」で登場し退場します。
⇒大河ドラマ2025年「べらぼう」第1話「ありがた山の寒がらす」のあらすじ(ネタバレ)と感想。
中島璃菜(役:二文字屋の女郎、ちどり)大河初出演。
吉原の周囲をめぐる「お歯黒どぶ」に沿って立ち並ぶ最下層の女郎屋が「河岸見世」。ちどりも行き場を失い河岸見世に転落した女郎の一人です。
年齢や病気、愛想のなさなど、さまざまな理由で行き場を失った女郎たちが集まる場所です。
⇒中島瑠菜(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう」で演じる「ちどり」とは。
稲垣来泉(役:大文字屋の振袖新造。かをり)大河初出演。
振袖新造と呼ばれる女郎見習いとして、先輩の女郎たちの付き人を務めながら諸芸を学んでいきます。
蔦重の恋心を隠さない天真爛漫な性格で、蔦重を見つけると必ず抱き着いてきます。後に吉原を代表する花魁「誰袖」へ成長します。
⇒稲垣来泉(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう」で演じる「かをり」とは。
福原遥(役:大文字屋の花魁。誰袖)17話で登場。
「かをり」と名乗った女郎見習いの頃から蔦重に恋心を抱き、吉原を代表する花魁になっても想い続けます。
何話で登場するかとても楽しみにしていましたが、5月4日放送の第17話「乱れ咲き往来の桜」で登場しました。
⇒福原遥(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう」で演じる「誰袖」とは。
山村紅葉(役:志げ)
大文字屋の「遣り手」で誰袖のお目付け役です。蔦重に想いを寄せる誰袖の恋の行く手を、阻もうとしています。
⇒山村紅葉(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる“志げ”とは。
東野絢香(役:玉屋の座敷持ち、志津山)
玉屋の座敷持ちの志津山は『一目千本』の中で「葛の花」として見立てられます。
⇒東野絢香(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう」で演じる「志津山」とは。
大塚萌香(役:「桐菱屋」の女郎亀菊)
第10話「青楼美人の見る夢は」で尾美さん演じる常富とアイコンタクトしていましたね。
新井美羽(役:女郎屋・松葉屋に売られてきた武家の娘・さえ)
第13話「お江戸揺るがす座頭金」で登場します。
新井美羽は「おんな城主直虎」で直虎の幼少期を演じました。当時は10歳でしたが、現在は18歳になりました。
⇒新井美羽(子役)が大河ドラマ2017年「おんな城主直虎」で演じる”おとは”とは?
さて、豪華絢爛な吉原の女郎の皆さんと横浜流星さんの蔦重を、アマゾンプライムビデオの「NHKオンデマンド」で視聴しましょう。
まだプライム会員になっていない大河ファンはお買い物の配送料が無料になり数多くの映画とドラマが視聴できるので登録することをお勧めします。
大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧。市井の人。
「べらぼう」では、主人公・蔦重を取り巻く江戸の庶民たちが物語に温度を与えますよね。
六平直政演じるそば屋の主人・半次郎は、人情味あふれる頑固親父で、蔦重の良き理解者です。
笑いも涙も受け止める存在として、吉原や日本橋の空気をぐっと身近にしてくれます。
市井の人々は豪商でも武士でもないが、蔦重の夢と挑戦を支える“江戸の心”。彼らの生き様が、物語に確かな生活の息遣いを吹き込んでくれます。
六平直政(役:そば屋の主人、半次郎)
五十間道、茶屋・蔦屋の向かいにある蕎麦屋“つるべ蕎麦”の主人です。幼いころから蔦重や次郎兵衛を見守ってきました。
⇒六平直政(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる半次郎とは。
東雲うみ(役:ひさ)
グラビアアイドルとしても活躍する東雲うみが演じる「ひさ」は、井之脇海が演じる小田新之助と同じ長屋に住む、手先の器用な娘です。
第9話「玉菊燈籠恋の地獄」で新之助が吉原の玉菊燈籠のイベントに連れてきました。
ドンペイ(役:座頭)
第13話「お江戸揺るがす座頭金」で登場します。
片桐仁(役:手先の器用な町人・弥七)
源内と一緒にレキテルを作っています。第13話「お江戸揺るがす座頭金」で登場します。
東雲うみ(役:ひさ)
源内と一緒にレキテルを作っています。第13話「お江戸揺るがす座頭金」で登場します。
大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト。語りは綾瀬はるか。
第1話のアバンでは“語り”だけでしたが、なんとアバン後にお稲荷さんの狐から花魁に化けての登場で吉原を紹介していました。
この演出も大河では初めての試みですね。
⇒綾瀬はるかは大河ドラマ2025年「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」稲荷で語りを担当。
大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧。蔦重と関係が深い人物。
蔦重は江戸のメディア王になりますが、吉原で出会う様々な人間との交流で確かな地位まで昇っていきます。
その代表が安田顕が演じる平賀源内です。また源内と一緒にいる新之助との出会いも蔦重の人生を大きく左右させます。
安田顕(役:平賀源内)16話で退場(死亡)
先ずは平賀源内です。
讃岐・高松藩の足軽の子として生を受けました。長崎への遊学などを通じて本草学(薬学)、蘭学、鉱山開発など多彩な知識を得ました。
幕府老中・田沼意次もほれ込む異才の男で、マルチな活躍をした男性です。蔦重の依頼で吉原への誘客に一役買います。
それは現代のコピーライトだったのです。
⇒安田顕(キャスト)が大河ドラマ「べらぼう 」で演じる平賀源内とは。
源内先生は第16話で退場しました。
⇒【源内獄中死】大河ドラマ「べらぼう」あらすじ(ネタバレ)と感想。第16話「さらば源内、見立は蓬莱(ほうらい)」
井之脇 海(役:小田新之助)12話で退場…と思ったら。33話で死亡。
新之助は元武士ですが、今は浪人の身です。源内の助手のような存在で、まじめな男です。
真面目だからこそ、吉原通いはしたことがありませんでした。しかし源内さんがある日お座敷に上がりその場にいたのが松葉屋の「うつせみ」でした。
新之助は一目ぼれでした。吉原の御法度である花魁との恋に陥り足受けを断行しますが、1度目は失敗でした。
ですが、数年後吉原の俄祭りで新之助はうつせみを見つけ吉原大門を通り抜け江戸市中に消えて行ったのです。
この12話で新之助は退場なのでしょうか?でもサプライズがありました。続きは井之脇海の記事で…
⇒井之脇 海(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる“小田新之助”とは。
第2章が始まった第17話で再登場し、唐丸(後の歌麿)と出合いきっかけを作ってくれました。
⇒【耕書堂繁盛の光と影】大河ドラマ「べらぼう」のあらすじ(ネタバレ)と感想。第17話「乱れ咲き往来の桜」
市原隼人(役:鳥山倹校)14話で退場。
盲目の大富豪で組織の大親分。高利貸しとして巨万の富を得て(瀬川=花の井)を身請けします。
身請けを決心した瀬川の最後の花魁道中は、白無垢で行い大門で待っている鳥山検校の元に嫁ぎました。
第10話「青楼美人の見る夢は」のエンディングで描かれました。
⇒市原隼人(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる“烏山検校”とは。
木村了(役:平秩東作)36話で退場(死亡)
内藤新宿の煙草屋で源内の相棒で山師でもあります。
⇒木村了(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる平秩東作とは。
大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧。クリエイターたち。
蔦重は、数多くの作家(戯作)・浮世絵師の作品をプロデュースし、江戸を中心とした町人文化・化政文化の隆盛に大きく寄与しました。
さらに、蔦重は企画・立案・編集・勧誘などのプロデュースだけではなく、自らを蔦唐丸の名で狂歌や戯作の制作も行い、その活動は多岐にわたります。
ここからは蔦重とともに活動した“クリエイター”たちを紹介します。
染谷将太(役:喜多川歌麿) 18話で登場。
鳥山石燕のもとで学び、寛政2年(1790年)頃から江戸の名だたる美女たちを描き始めた「美人大首絵」で大いに人気を集めました。
その繊細で美しい画風は多くの人々を魅了し、蔦屋重三郎との出会いにより不動の人気を得ました。
歌麿の幼少時代は蔦重の店で働いていた唐丸でした。染谷さんが演じる歌麿は第18話で登場します。
⇒【歌麿登場】大河ドラマ「べらぼう」のあらすじ(ネタバレ)と感想。第18話「歌麿よ、見徳は一炊夢」
⇒染谷将太(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる喜多川歌麿とは。
尾美としのり(役:朋誠堂喜三二(ほうせいどうきさんじ) 本名は平沢常富。
出羽・久保田藩の定府藩士で江戸留守居です。「宝暦の色男」を自称し、吉原へ通い続け、その経験を生かした作品を多く刊行しました。
ドラマの1話から9話までは一瞬の出演や回想なので見つけることが困難でしたが、第10話「青楼美人の見る夢は」ではっきり映っていました。
この時までセリフはありませんが、花魁と目線で会話していましたよ。
⇒尾美としのり(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる平沢常富とは。
古川雄大(役:山東京伝(さんとうきょうでん) 本名は岩瀬醒)
作家として活躍するだけでなく、現代でいう銀座1丁目に喫煙用の小物販売店「京屋」を開業し、自らデザインした紙製煙草入れを大流行させました。
深川木場生まれで、北尾重政に絵を学び、その後徐々に洒落本や黄表紙などを手がけ鶴屋が出した「御存商売物」で、戯作者としての地位を確立します。
蔦重とは、度々吉原に出入りするなかで知り合い、親交を深めていきます。
「江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)の大ヒット以降、蔦重のパートナーとして欠かせない存在となっていきます。
第13話で初登場。
⇒古川雄大(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる山東京伝とは。
岡山天音(役:倉橋 格 /恋川春町)19話で本格登場し36話退場(切腹)。
喜三二の親友で、黄表紙の傑作「金々先生栄花夢(きんきんせんせいえいがのゆめ)の作者です。
倉橋 格(くらはし・いたる)/恋川春町 ( こいかわ・はるまち)は駿河小島藩に仕える武士で、挿絵も文章も書ける戯作者です。
鱗形屋孫兵衛から出した「金々先生栄花夢」は大ヒットし、その後に続く黄表紙の先駆けとなります。
本屋の新参者の蔦重とは、親交のあった朋誠堂喜三二の仲介で知り合います。(5月18日放送の第19話で二人は会います)
⇒【鱗形屋廃業】大河ドラマ「べらぼう」のあらすじ(ネタバレ)と感想。第19話「鱗(うろこ)の置き土産」
蔦重とは次々と作品を出すものの、時代の変わり目で発表した「鸚鵡返文武二道」が、幕府の目に留まり、思わぬ事態となっていきます。
初登場は第11話「富本、仁義の馬面」でした。
⇒岡山天音(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる恋川春町とは。
桐谷健太(役:四方赤良(あから)本名は大田南畝)20話で登場。
無類の酒好きで、20話で登場します。蔦重に酒をすすめるシーンがありますが、蔦重は飲みすぎてしまいべろべろになってしまいました。
勘定所に勤務する幕府官僚であり、江戸では名の通った文筆家で、杏花園(きょうかえん)・蜀山人(しょくさんじん)などと号して多数の狂歌本や戯作を刊行しました。
「大田南畝(おおた・なんぽ) /四方赤良 (よもの・あから)」は牛込の御徒組屋敷で生まれ育った幕臣です。
十代で出した狂詩集「寝惚先生文集」で一躍その名をとどろかせ、その後「四方赤良」という狂名で、天明狂歌をけん引する存在となります。
批評家、戯作者など多彩な一面も持ち合わせ、蔦重とは、南畝が書いた黄表紙評判記「菊寿草」をきっかけに、交流がスタートします。
⇒桐谷健太(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる大田南畝とは。
片岡鶴太郎(役:鳥山石燕)18話で登場、35話で退場(死亡)
鳥山石燕(とりやま・せきえん)は、妖怪画の大御所、歌麿の人生に大きな影響を与えた師です。
徳川将軍家に仕える狩野派に絵を学び、安永5年(1776年)に「画図百鬼夜行」を刊行し、妖怪画の名手として注目をあびます。
喜多川歌麿や恋川春町など数多くの弟子を持ちます。 特に歌麿には、小さいころから目をかけ、その“才能の目覚め”にきっかけを与えたのです。
⇒片岡鶴太郎(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる鳥山石燕とは。
ジェームス小野田(役:狂歌師・元木網=もとのもくあみ)大河ドラマ初出演
大田南畝らとともに活躍した人物です。(4月15日発表)
狂歌(きょうか)とは、世相を風刺したり、洒脱な言葉遊びで人々を笑わせたりする、江戸文化の粋を凝らした短詩です。
その世界で名を馳せたのが元木網(もとのもくあみ) です。
大河「べらぼう」では、蔦重が生きた“寛政期の文化サロン”を象徴する存在として登場します。
ジェームス小野田さん(米米CLUB)が持つ独特のユーモアとエネルギーが、狂歌師の奔放さと見事に重なっていますね。
寛一郎(役:富本午之助=富本豊前太夫)
富本午之助 (とみもと・うまのすけ)は、その美声で観衆を虜(とりこ)にする、江戸浄瑠璃の歌い手です。
富本豊前掾(とみもとぶぜんのじょう)を父に持ち、二代目「富本豊前太夫」を称します。
蔦重が当時流行していた富本節を正本にしようと、接触を試みる富本の二代目で、別名を“馬面太夫”と言います。
寛一郎は大河ドラマ「鎌倉殿の13人」でも登場した大物俳優「佐藤浩市」の息子です。
濱尾ノリタ(役:市川門之助)
富本豊志太夫(午之助)とともに、芝居小屋で活躍する歌舞伎役者・市川門之助(いちかわもんのすけ)
山中 聡(役:杉田玄白)
杉田玄白 (すぎた・げんぱく)は、「解体新書」の生みの親であり、源内とも親交がありました。
若狭小浜藩の範医で、前野良沢や中川淳庵とともに、「ターヘル・アナトミア」を翻訳し、須原屋から「解体新書」を発表します。
平賀源内は、「解体新書」の挿絵を描くことになる画家・小田野直武を紹介し、活躍する分野は異なっても、互いに尊敬しあう仲となっていきます。
山口森広(役:唐来三和)
ユーモアのセンスにたけた、江戸の戯作者である唐来三和 (とうらい・さんな)は、もともとは武士の出身でした。
しかし、天明期に訳あって町人となり、絵師、狂歌師、戯作者たちを集めた大規模な宴席で、蔦重と出会います。
代表作に「莫切自根金生木(きるなのねからかねのなるき)、題名が上から読んでも下から読んでも同じの回文の傑作があります。
やがて松平定信の時代に変わると、自ら発表した作品が政治批判をしたとされ絶版処分を受けてしまいます。
⇒山口森広(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる唐来参和(三和)とは。
浜中文一(役:朱楽菅江)
朱楽菅江(あけら・かんこう)は、 大田南畝、唐衣橘洲(からごろも・きっしゅう)とともに、狂歌三大家の一人です。
大田南畝らと共に始めた狂歌が、天明期に大流行し、そのブームをけん引する一人となります。蔦重とは、大田南畝に誘われて行った、狂歌の会で出会います。
その後、狂歌本を何冊も蔦重のもとから出し、喜多川歌麿とのコラボ作品も世に送り出していくのです。
⇒浜中文一(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じるとは。
橋本淳(役:北尾重政、絵師)
独学で浮世絵を学び、北尾派の開祖となります。蔦屋と北尾派の関係は根強く、多数の作品を刊行しました。
⇒橋本淳(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる北尾重政とは。
前野朋哉(役:勝川春章、絵師)
いつしか江戸深川の絵師・宮川春水の門下に入り、春章と名乗ります。勝川派の祖で葛飾北斎の師です。
10週の「青楼美人」で登場します。
浮世絵師・北尾重政(きたおしげまさ)との競作による、吉原の遊女たちの艶姿を描いている錦絵本を創作します。
いわば遊女たちのパンフレットですね。
物語では吉原の忘八の親父さんたちが瀬川が身請けするにあたり最後の花魁姿の錦絵を蔦重に頼むのです。
そこで、蔦重は北尾と勝川にその制作依頼をすのです。
⇒前野朋哉(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる勝川春章とは。
鉄拳(役:礒田湖龍斎)
第4話で蔦重は女郎たちの錦絵の作成を親父衆から任されます。その絵師が美人画を得意とする鉄拳が演じる「磯田湖龍斎」です。
⇒鉄拳(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる礒田湖龍斎とは。
水樹奈々(役:狂名“智恵内子=ちえのないし)大河初出演。20話で登場。
湯屋の主人・元木網の妻・すめで、狂名は“智恵内子(ちえのないし)です。(4月15日発表)
加藤虎ノ介(役:北川豊章=絵師)18話で登場。
加藤虎ノ介が演じる北川豊章は第18話「歌麿よ、見徳は一炊夢」で登場します。
蔦重が北川豊章という絵師が描いた数枚の絵を見比べるうちに、この絵は唐丸が書いたのではないか?との考えが浮かびます。
早速、豊章が住む長屋を訪ねると、そこにいたのは、捨吉(=唐丸、後の歌麿)と名乗る男でした。
又吉直樹(役:宿屋飯盛)
大田南畝に学び、狂歌四天王の一人に数えられた狂歌師で、日本橋で宿屋を営んでいたことが狂名の由来です。
狂歌集の編集・出版で蔦重と協力し、 天明8年には、歌麿とともに 狂歌絵本『画本虫撰(えほんむしえらみ)』を刊行し、 狂歌師の地位を不動のものにしました。
蔦重が亡くなった後、蔦重の墓に碑文を残しています。
井上芳雄(役:十返舎一九(じっぺんしゃいっく) 本名は重田貞一)
家系や出生には不明な点が多い人物です。蔦重の死後、享和2年(1802年)に「東海道中膝栗毛」が大ヒットして流行作家となりました。
9月15日(月)NHKから井上義雄さんのキャスティングが発表になりました。
駿河国の生まれで、ある日、日本橋の蔦重のもとに訪ねてきます。蔦重が出す黄表紙が好きで、自らも耕書堂で、本を書きたいと申し出るのですが…。
史実では、蔦重亡き後に執筆した『東海道中膝栗毛』が全国的に多くの読者を獲得して滑稽本という新たなジャンルを確立した人物です。
44話「空飛ぶ源内」で登場します。
くっきー!(役:勝川春郎後の葛飾北斎)
9月15日(月)NHKから井上義雄さんのキャスティングが発表になりました。勝川春朗(かつかわ・しゅんろう)のちの葛飾北斎(かつしかほくさい)です。
「冨嶽三十六景」などで知られる天才絵師・葛飾北斎は、その斬新かつ大胆な作風は、国内はもちろん海外でも広く愛されています。
90歳で人生の幕を閉じるまで勢力的に絵を描き続け、自ら“画狂老人”と名乗った浮世絵界の巨匠です。
史実では、蔦重亡き後も画号を幾度も改めながら、独自の表現を追い求め続けました。絵の描き方を教える入門書なども手がけ、従来の浮世絵の枠を超えて、人々から高く評価されました。
津田健次郎(役:滝沢瑣吉後の曲亭馬琴)大河初出演。
9月15日(月)NHKから井上義雄さんのキャスティングが発表になりました。
江戸の大ベストセラー『南総里見八犬伝』を書いた、異才の戯作者滝沢瑣吉(たきざわ・さきち)、のちの曲亭馬琴(きょくていばきん)です。
北尾政演と山東京伝の紹介で、しばらくの間、蔦重の耕書堂に手代として世話になることにまります。
そこで働く傍ら、戯作者として黄表紙の執筆を始めます。蔦重は新たな才能を競わせようと、勝川春朗とのコンビを組ませますが…。
史実では、二十八年もの歳月を費やして伝奇小説『南総里見八犬伝』を完成させ、その愛読者は近代にまで及ぶベストセラーとなります。
登場しません。(役:歌川広重)
広重の最盛期には蔦重や歌麿はこの世を去っていたので、「べらぼう」では登場することはないでしょう。
歌川広重は天保年間(1830~44年)に風景画で人気を博し、その後日本国内だけでなく西洋芸術にも影響を与えた浮世絵師です。
代表作は、江戸から京都までの宿場町の風景を描いた作品群「東海道五十三次」。
広重の風景画には多くの海や川、湖などの水辺が描かれ、特に青色の美しさは“広重ブルー”と称されています。
キャスト不在(役:幻の東洲斎写楽)
蔦重がプロデュースした今も人気の浮世絵師・東洲斎写楽とはどんな人物だったのでしょう?。
寛政6年(1794年)から寛政7年(1795年)の10ヵ月にかけて149作品の役者絵を蔦屋から刊行しました。
歌舞伎役者の半身像を描いた「大首絵」28図を一挙に出版した東洲斎写楽は、彗星のように現れ一世を風靡しましたが、その後140点におよぶ浮世絵を世に送り出して姿を消しました。
来歴が不明でその正体は今も謎に包まれている浮世絵師です。その姿は森下脚本の第45話で見て下さい。
登場しません。(役:菱川師宣(ひしかわもろのぶ)
浮世絵師。
しなやかな曲線と繊細な色使いで描かれた肉筆画「見返り美人図」などが有名で、“師宣の美女こそ江戸女”と称賛されました。
師宣は、それまで古典や物語などの挿絵で使われていた版画を1枚の絵画として魅力ある作品へ進化させ、木版画で大量生産し大衆化させることに成功した人物です。
絵を所有する喜びを多くの庶民が味わえるようになると、絵の題材も目の前にある「今のこの世=浮浮世絵」へと変化していきます。
師宣はあらゆる階層の人々が生きる姿を鮮やかに描き、“浮世絵の祖”と呼ばれています。
さて、蔦重を支えた江戸時代のクリエイターの面々をアマゾンプライムビデオの「NHKオンデマンド」で視聴しましょう。
まだプライム会員になっていない大河ファンはお買い物の配送料が無料になり数多くの映画とドラマが視聴できるので登録することをお勧めします。
大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧。本屋たち。
蔦重こと蔦屋重三郎は、吉原の案内本「吉原細見」や女郎たちの姿を描いた本を大いに広めて吉原の街に人を呼ぼうと意気込みます。
その為には江戸の本屋に売り込まなければなりません。しかし、江戸の出版業界は手練れの本屋がしのぎを削る世界で曲者ぞろいでした。
蔦重と一戦交えることとなる江戸の本屋とは。
片岡愛之助(役:鱗形屋孫兵衛)19話退場(鱗形屋廃業)
蔦重と敵対する地本問屋の主人です。鱗形屋の先祖は大人が楽しめる絵入りの娯楽本である「青本」を開拓し江戸で広めました。
⇒片岡愛之助(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう」で演じる「鱗形屋孫兵衛」とは。
鱗形屋は5月18日放送の19話で蔦重と和解し退場します。
鱗の置き土産とはこの版木で、蔦重が幼いころ最初に買った赤本の版木だったのです。蔦重と鱗形屋はこの版木で結ばれていたのですね。
⇒【鱗形屋廃業】大河ドラマ「べらぼう」のあらすじ(ネタバレ)と感想。第19話「鱗(うろこ)の置き土産」
徳井優(役:鱗形屋の番頭、藤八)
先代の頃から鱗形屋を支えてきた年寄り番頭です。
⇒徳井優(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる藤八とは。
三浦獠太(役:鱗形屋孫兵衛の長男、長兵衛)19話で退場。
⇒三浦獠太(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる鱗形屋長兵衛とは。
風間俊介(役:鶴屋喜右衛門)
蔦重に立ちはだかる、江戸市中の地本問屋のリーダー的存在です。
⇒風間俊介(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる鶴屋喜右衛門とは。
西村まさ彦(役:西村屋与八)
蔦重のライバル。地本問屋の主人。
⇒西村まさ彦(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる西村屋与八とは。
芹澤興人(役:小泉忠五郎)
蔦重の「吉原細見」に西村屋と組んで対抗します。
⇒芹澤興人(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる小泉忠五郎とは。
里見浩太郎(役:須原屋市兵衛)
蔦屋に手を貸し、応援します。書物問屋の主人です。
⇒里見浩太郎(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる須原屋市兵衛とは。
大河ドラマ「べらぼう」に出演するキャストの配役一覧でした。そのキャストさんが活躍するあらすじ一覧はこちら。
⇒大河ドラマ2025年「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」のあらすじ(ネタバレ)感想まとめ。
中川翼(役:地本問屋・丸屋の手代・みの吉)
中川翼は3度目の大河ドラマ出演です。(4月15日発表)
中井和哉(役:地本問屋・岩戸屋源八)
声優、中井和哉は江戸の地本問屋・岩戸屋源八を演じます。5月25日放送のべらぼう第20話「寝惚(ねぼ)けて候」で登場しました。
中井和哉は人気アニメ「ONE PIECE(ワンピース)」のロロノア・ゾロ役などで知られる声優です。
20話では蔦重と対立する日本橋・地本問屋にもの申す役でした。
と言うのも、岩戸屋は、江戸市中でみんなが面白がってるものを提供したい商売人の魂があったと思います。
ユーザーが面白いと思っている、本屋も面白いって思っている、それが江戸で評判の「蔦重の耕書堂が出した本」を取り扱えないことに不満を抱いていたのです。
さて、その本屋の皆さんをアマゾンプライムビデオの「NHKオンデマンド」で視聴しましょう。
まだプライム会員になっていない大河ファンはお買い物の配送料が無料になり数多くの映画とドラマが視聴できるので登録することをお勧めします。
大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧。徳川家。
時は10代将軍・徳川家治の時代です。
祖父の8代将軍・徳川吉宗から帝王学を授かった彼を取り巻くのは、江戸幕府の威光を維持すべき創設された「御三卿」や大奥の人々です。
眞島秀和(役:10代将軍・徳川家治)31話で退場(死亡)
徳川家治は、九代将軍・家重が、言語不明瞭で体が弱かったため、八代将軍・吉宗の英才教育を幼いころから受けてきました。
家重の遺言に従い田沼意次を側用人に重用し、松平武元らとともに政治に励むのです。将棋を趣味として、その腕前は高く、将棋を通じて意次との絆を深めたといわれています。
⇒眞島秀和(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる徳川家治とは。
城桧吏:(役:11代将軍・徳川家斉)。32話で登場。
「べらぼう」は大河ドラマ64作品目ですが、徳川幕府の歴代将軍で登場していなかった将軍は10代将軍と11代将軍でした。
10代将軍・家治は眞島さんがべらぼうで演じましたので、11代将軍が登場すれば「徳川15将軍コンプリート」となります。
その11代将軍家斉(いえなり)を城桧吏(じょう・かいり)さんが演じます。実力派俳優のキャスティングですね。
7年前の2018年にカンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した『万引き家族』の子供役(柴田祥太役)で注目を集めましたのでファンはたまりません。
どんな「家斉」を演じてくれるのでしょうか…楽しみですね。登場話は現時点では分かりませんが、いずれにしても10代将軍が去られた後だと思います。
8月後半で登場話が分かりました。
⇒【米の高騰】大河ドラマ2025年「べらぼう」第32話「新之助の義」のあらすじ(ネタバレ)と感想。
10代将軍・家治、11代将軍・家斉が「べらぼう」で登場したことで大河ドラマで徳川15代将軍がコンプリートされました。
冨永愛(役:大奥取締役高岳=たかおか)
大奥筆頭老女の高岳は、田沼意次、松平武元と並び幕府の実権を握る大奥の最高権力者です。
賢丸の妹の種姫を十代将軍・家治の養女として迎え、家治の嫡男・家基の正室とするよう画策します。
⇒冨永愛(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる高岳とは。
奥智哉(役:徳川家基)15話で退場(死亡)
徳川家基は、幼いころより聡明で成長するにつれて政治に関心を持ち、田沼意次の政策を批判します。
十一代将軍として将来を期待されるが、鷹狩(たかがり)に出かけた折に体調不良を訴え、“謎の死”を遂げます。
徳川宗家の歴史の中で「家」の通字を授けられながらも唯一将軍位に就くことができませんでした。
第15話「死を呼ぶ手袋」で鷹狩の途中で変死し退場でした。
⇒奥智哉(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる徳川家基とは。
高梨臨(役:知保の方)
知保の方は、十代将軍・家治の側室です。
家治は正室・五十宮との間に永らく子ができなかったが、側室を持つことを拒み続けていました。 しかし意次の強い後押しで知保の方は家治の側室となり、家基を出産します。
長子出産の功労から「老女上座」の格式を賜ります。
⇒高梨臨(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる知保の方とは。
生田斗真(2役:一橋治済/斎藤十郎兵衛)
一橋治済は、八代将軍・吉宗の後継者対策に端を発して作られた「御三卿」のひとつ一橋徳川家の当主です。
吉宗の孫にあたり、十代将軍・家治とは“いとこ”ですね。
次々と将軍後継者が早世する中、最後に残った治済の息子・家斉が十一代将軍となり、治済は「将軍の父」としてすべての富と権力を得るようになります。
さて、さて、森下佳子さんの驚きの脚本が最終話48話の前週の47話で描かれます。なんと生田斗真さんが2役演じるのです。
その男は昨今の研究で写楽ではないか?と言われている「斎藤十郎兵衛」です。
⇒生田斗真(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる一橋治済とは。
寺田心(役:田安賢丸=松平定信)
田安賢丸は、幼少期より聡明で、兄たちが体が弱かったため、若くして田安家の後継者になります。 また、十代将軍・家治の後継と目されていました。
陸奥白河藩の養子にむかえられ、幕政の中心から遠のくも、田沼意次の失脚後は十一代将軍・家斉の命で老中となり、寛政の改革を行います。
寛政の改革では、風紀の取り締まりから蔦屋重三郎に厳しい処分を科すこととなります。
⇒寺田心(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる田安賢丸(松平定信)とは。
井上祐貴(役:松平定信)
寺田心さんが演じた田安賢丸が成長し、松平定信となります。その定信を演じるのは、「どうする家康」で本多正純を演じた井上祐貴さんです。
定信は34話「ありがた山とかたじけ茄子」で老中首座に就任し質素倹約を主とする「寛政の改革」に取り組みます。
ここから蔦重の出版規制にもつながるのですが、どんな演出になるのか楽しみですね。
⇒【質素倹約に抗う蔦重】大河ドラマ2025年「べらぼう」第34話「ありがた山とかたじけ茄子」のあらすじ(ネタバレ)と感想。
小田愛結(役:種姫、松平定信の妹)
3月9日放送の第10話「青楼美人の見る夢は」でのエンディングで、種姫がある種を賢丸に持ってきます。
その種を見て賢丸は「田安の種をまけばいいのです! 江戸城に!!」とのヒントを得ました。
その幼い種姫の愛らしい容姿を見た視聴者からは「種姫とっっても可愛いらしい」「種姫役の小田愛結ちゃん、あの髪型似合ってて可愛い」とのコメントがありました。
初登場は第4話「雛(ひな)形若菜の甘い罠(わな)」です。
花總まり(役:宝漣院)
宝蓮院は、御三卿・田安徳川家初代当主・宗武の正室です。
のちに松平定信となる賢丸を、白河松平家の名君、「寛政の改革」を行った老中となるまでに育てた「母」です。
宗武の七女・種姫を次期将軍となる家基の正室にするため、十代将軍・家治の養女として送り込みます。
⇒花總まり(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる法蓮院とは。
映美くらら(役:大崎)
大崎は、十一代将軍・家斉の乳母で、家斉の将軍就任後、大奥で絶大な権力を持ったといわれています。
⇒映美くらら(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる大崎とは。
高橋秀樹(役:徳川治貞)
高橋秀樹さんは「べらぼう」で第10作目の大河ドラマ出演になりますね。(4月15日発表)
徳川御三家紀州藩の第9代藩主・徳川治貞を演じます。
さて、その徳川家の面々をアマゾンプライムビデオの「NHKオンデマンド」で視聴しましょう。
まだプライム会員になっていない大河ファンはお買い物の配送料が無料になり数多くの映画とドラマが視聴できるので登録することをお勧めします。
大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧。幕臣と旗本。
「べらぼう」では、江戸城で政を担う老中・旗本たちが物語に重厚さを添えてくれます。
渡辺謙が演じる田沼意次は、卓抜した経済政策で時代を動かす巨魁。
対する井上祐貴演じる松平定信は、清廉な理想を掲げ改革に挑む若き権力者。二人の思想と情がぶつかり合うことで、蔦重の生きる町方の世界にも波紋が広がります。
江戸城の男たちは、政治の光と影を映し出し、ドラマの緊張感を一気に引き上げる存在なのです。
渡辺謙(役:田沼意次)34話で失脚。
田沼意次は江戸時代中期の徳川幕府の老中として活躍した政治家です。
自らの才能と実行力で、足軽出身の出自から遠江相良藩(いまの静岡県牧之原市)の五万七千石の大名に昇りつめた人物です。
「米」による幕府の財政運営に限界をおぼえ、金を動かしてこそ“経済がまわる”商業重視の政策に方針を大転換します。
商人を中心に江戸は好景気に沸きました。
また印旛沼の干拓、蝦夷地の開発、優秀な人材を幕政に積極的に登用し、“新しい日本”を創り始めるのです。
意次の政策は、商業や産業を活用した経済成長を目指す挑戦的なものでした。
大河べらぼうでは意次は定信が首座老中になったことで失脚することになりました。
⇒渡辺謙(キャスト)が大河ドラマ「べらぼう 」で演じる田沼意次とは。
宮沢氷魚(役:田沼意知)
田沼意知は、田沼意次の嫡男です。田沼権勢の象徴として、若くして意知は若年寄に昇進し、異例の出世をとげます。
意次が着々と実行してきた改革を、より推進し、政治的手腕を発揮、蝦夷開発にも積極的に携わっていきました。
また、江戸の町を度々見聞するなど好奇心旺盛な一面も持っています。
しかし、父・意次の正統な後継者と思われていた矢先、江戸城内で予期せぬ事件に巻き込まれてしまうのです。
⇒宮沢氷魚(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる田沼意知とは。
栁 俊太郎(役:勘定組頭・土山宗次郎 )
意次の側近である土山宗次郎 (つちやま・そうじろう)は政変により人生を狂わされた武士です。
田沼意次の家臣で、勘定組頭の旗本で、意次が蝦夷開発を積極的に推進するなかで、その探査役として、大きく関わっていました。
また吉原での豪遊も絶えず、大田南畝のパトロンとして、贅沢の限りを尽くし、やがて大文字屋の花魁・誰袖(たがそで)を1200両という莫大な金額で身請けします。
しかし、意次が失脚すると、悲運な人生をたどっていくのです。
原田泰造(役:三浦庄司)
三浦庄司は、備後国福山藩(現在の広島県福山市)出身の農民から田沼家の用人となった人物です。
意次の側近として、意知、松本秀持とともに政策を立案主導していく人物です。
⇒原田泰造(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる三浦庄司とは。
宮尾俊太郎(役:田沼意致)
バレエダンサーの宮尾俊太郎が、意次のおいである意致(おきむね)を演じます。10代将軍・家治の嫡男・家基について西の丸目付となり、その後一橋家の家老になります。
田沼と一橋をつなぐ役目を果たし、治済の子・豊千代の11代将軍就任に尽力します。
中村隼人(役:旗本・長谷川平蔵宣以)
長谷川平蔵の本名は長谷川宣以(のぶため)で平蔵は通称です。江戸時代中期の旗本で、寛政の改革期に火付盗賊改役を務め、人足寄場を創設しました。
青年時代は風来坊で「本所の銕(てつ)」」と呼ばれ、遊里で放蕩(ほうとう)の限りを尽くしたという逸話も持ちます。
「べらぼう」の前編では風来坊の平蔵が描かれますね。
のちに老中・松平定信に登用され「火付盗賊改方」を務め、凶悪盗賊団の取り締まりに尽力します。
その人柄も相まって庶民から「今大岡」「本所の平蔵様」と呼ばれて絶大な人気を誇りました。
⇒中村隼人(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう」で演じる「長谷川平蔵」とは。
吉沢悠(役:旗本・松本秀持)
松本秀持は、身分の低い家柄であったが、田沼意次に抜てきされ勘定奉行となり、印旛沼・手賀沼の干拓事業や経済政策などに従事します。
また蝦夷地調査を意次に上申し、調査隊を派遣することになります。
⇒吉沢悠(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる松本秀持とは。
石坂浩二(役:老中・松平武元)16話で退場(死亡)
松平武元は老中首座です。 吉宗、家重、家治の将軍三代に仕え、家治からは「西の丸の爺」と呼ばれ信頼されていました。
上野国館林藩主でもあり、その官位から「右近将監(うこんのしょうげん)」様と呼ばれ、敬愛を集めた人物です。
⇒石坂浩二(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう」で演じる「松平武元」とは。
相島一之(役:松平康福)
松平康福は、石見国浜田藩主、下総国古河藩主、三河国岡崎藩主、そして浜田藩主とたびたび国替えを経験した武士です。
娘を意知に嫁がせ、田沼意次とは親戚関係となります。意次の失脚後も松平定信の老中就任や寛政の改革に最後まで反対したといわれています。
⇒相島一之(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる松平康福とは。
矢本悠馬(役:旗本・佐野政言)
佐野政言の佐野家は三河以来、徳川家に仕えた歴史があります。代々番士を務めた家柄で、江戸城内で若年寄の田沼意知に切りつけ、重傷を負わせ絶命させました。
幕府は「私憤からの乱心」として切腹を命じるが、庶民からはこれを「世直し大明神」と称えられることになるのです。
⇒矢本悠馬(キャスト)が大河ドラマ2025年「べらぼう 」で演じる佐野政言とは。
日野陽仁(役:西の丸小姓組・森忠右衛門)
井上和彦(役:奉行)
第14話「蔦重瀬川夫婦道中」で登場します。井上さんは声優の大御所ですね。
大文字屋は神田に屋敷を買おうとしていたが、手付金を払ったところで町名主から横やりが入り、断られてしまいます。
そこで奉行所に訴え出たものの、奉行からは「そもそも吉原者は四民の外」として市中に家屋敷を買うことは許されないと断じられたのです。
その奉行を演じました。
ひょうろく(役:松前藩の江戸家老・松前廣年)大河初出演。
4月15日発表。
えなりかずき(役:松前廣年の兄・道廣)大河初出演。
2025年4月15日に発表がありました。第21話「蝦夷桜上野屁音」でラスボス的な演出で登場します。
⇒【蝦夷地利権】大河ドラマ「べらぼう」のあらすじ(ネタバレ)と感想。第21話「蝦夷桜上野屁音」
「えなりかずき」が演じる「松前道廣」とは…
⇒えなりかずき(キャスト)が「べらぼう 」で演じる松前藩の松前道廣とは。
田中幸太朗(役:島津家当主・島津重豪)
第20話「寝惚けて候」で登場します。
薩摩藩第8代藩主で、江戸後期の開明的な大名です。娘・茂姫を将軍家斉の正室に、“政略結婚”で幕政に強く食い込もうとする外交戦略家です。
「べらぼう」では第20話にて登場し、田沼意次が進める将軍後継案に激しく反発する姿が描かれました。
島津重豪は歴史上でも洋学・蘭学に理解があり、開明派としても知られますが、ドラマ内でもワインにうんちくを述べるシーンがありましたね。
“政治的黒幕”のひとりとして強烈な存在感を放っています。田沼意次、一橋治済との思惑が交差する中、今後の動きにも注目していきましょう。
井上祐貴(役:松平定信)
後半の「べらぼう」で井上祐貴が演じる松平定信は、若き改革者としての理想と、政治の闇に翻弄される現実の狭間でもがき続ける存在でした。
寛政の改革によって町人文化を抑え込みつつも、その根底には“正しい世を作りたい”という純粋な信念があったのです。
しかし一橋治済との権力闘争に敗れ失脚すると、その静かな怒りと未練が、蔦重との奇妙な共闘へとつながっていくシナリオでしたね。
清廉さゆえに孤立し、孤立ゆえに燃え上がる執念。
井上祐貴の定信は、若さと苛烈さが同居した、後半の物語を大きく揺さぶるキーパーソンとして際立った存在でした。
さて、その幕臣・松平定信をアマゾンプライムビデオの「NHKオンデマンド」で視聴しましょう。
まだプライム会員になっていない大河ファンはお買い物の配送料が無料になり数多くの映画とドラマが視聴できるので登録することをお勧めします。
大河ドラマ「べらぼう」出演キャスト一覧のまとめ。
大河ドラマ2025年「べらぼう」は、蔦屋重三郎を中心に“本で世を耕す”(耕書堂)という情熱が、江戸の隅々にまで広がっていく群像劇です。
蔦重を支えた歌麿・春町・京伝らクリエイターは、苦境にも筆を折らず、表現の自由を追い求めた反骨の才人たちでした。
吉原の花魁や女郎たちは、華やかさの裏で切なさと誇りを抱え、時に蔦重の心を動かしました。
忘八や商人たちは、欲としがらみの中で生きる“江戸のリアル”を体現してくれました。
さらに田沼意次、松平定信、一橋治済ら武士たちの権謀術数が物語に強烈なうねりを加えて多彩なキャストが織りなす、江戸という巨大なドラマが息づいた作品でした。
さて、横浜流星の蔦重や、豪華絢爛な吉原の女郎の皆さんをアマゾンプライムビデオの「NHKオンデマンド」で視聴しましょう。
まだプライム会員になっていない大河ファンはお買い物の配送料が無料になり数多くの映画とドラマが視聴できるので登録することをお勧めします。
大河ドラマ俱楽部の管理人です。
NHK大河ドラマをこよなく愛し毎週楽しみに視聴しています。
ただ視聴するだけでなく「あらすじと感想」を紹介しています。
でもリアルタイムで見ることができない時は見逃し配信で見たり
時々は歴代の大河も視聴しています。
また、管理人の大好きな大河ドラマ出演者の他のドラマや映画を
まとめていますので見逃し配信と一緒に楽しんで下さい。
※大河ドラマ倶楽部は、Amazonの商品を紹介することで紹介料
を頂くAmazonアソシエイト・プログラムの参加者です。